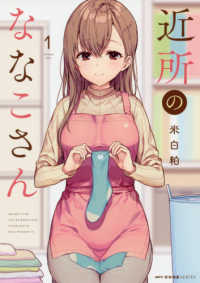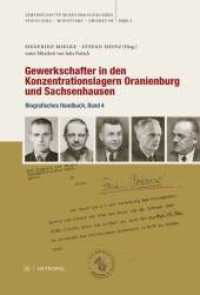出版社内容情報
人間vs.将棋・囲碁ソフトの激闘史から読み解くヒトとAIの未来!将棋および囲碁ソフトとプロ棋士が対局する「電王戦」。その激闘の歴史を、棋士・ソフト開発者双方の視点で振り返りながら、コンピュータ=AIがどのような発展を遂げてきたのか、これからどこへ向かおうとしてきたのか、また人間がその開発にどのような苦労、思想で望んできたのか、さらに対する側の人間がどう対処してきたのか、などを将棋とITに詳しい筆者が考察する。
内容説明
二〇一七年四月一日、現役タイトル保持者が、はじめてコンピュータ将棋ソフトに敗れた。AI(人工知能)が、ついに人間の王者を上回ったのだ。それは予想だにしない奇跡だったのか、それとも必然だったのか?コンピュータ将棋の開発が始まってから四十年あまり、当初、「人間に勝てるはずがない」ともいわれたコンピュータ将棋は、驚異的な進化を遂げて、いま、人間の前に立ちはだかる。この間、棋士は、そしてソフト開発者は何を考え、何をめざしてきたのか?そして、人間とAIは、どのような関係へと向かうのか?将棋界の最前線を十数年取材してきた将棋記者の、渾身のルポルタージュ!
目次
第1章 神が創りたもうたゲームの系譜(囲碁・将棋の歴史を振り返る;幕を開けた人間と機械の戦い)
第2章 電王戦前夜―人間vsコンピュータの始まり(コンピュータ将棋の黎明期;人間を凌駕するコンピュータ;人智を超えた“学習する”将棋ソフト)
第3章 AIが人間を超えた日(女流トッププロvsコンピュータ連合軍;第一回電王戦;第二回電王戦;第三回電王戦)
第4章 苦闘―棋士の葛藤と矜持(電王戦FINAL;FINAL最終戦に見た両者の信念)
第5章 棋士とAIの未来(新たにスタートした第一期電王戦;第二期電王戦;AIとの苦闘が残すもの)
著者等紹介
松本博文[マツモトヒロフミ]
将棋中継記者。1973年山口県生まれ。93年、東京大学に入学。東大将棋部に所属し、在学中より将棋書籍の編集に従事。東大法学部卒業後、名人戦棋譜速報の立ち上げに尽力し、「青葉」の名で中継記者を務め、日本将棋連盟、日本女子プロ将棋協会(LPSA)などのネット中継に携わる。コンピュータ将棋の進化を描いたデビュー作『ルポ電王戦』(NHK出版新書)が話題となり、第27回将棋ペンクラブ大賞(文芸部門)を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
starbro
しーふぉ
izw
Humbaba
アキオ