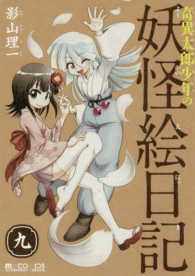内容説明
メディアで話題の探険昆虫学者が中米の楽園で出会った強烈なインパクトを放つ虫たち!!
目次
第1章 ツノゼミ(ミカヅキツノゼミの一種(ツノゼミ)
ハチマガイツノゼミの一種(ツノゼミ) ほか)
第2章 キリギリス・バッタ(カエノランピス・ロベルツィ(カタハダバッタ)
ミメティカ・クレヌラタ(ヒラタツユムシ(キリギリス)) ほか)
第3章 甲虫・カメムシ(オモラブス・クアドラトゥス(オトシブミ)
フィソノータの一種(ジンガサハムシ) ほか)
第4章 チョウ・ガ(ベニモンシジミタテハの一種(シジミタテハチョウ)
ウラモジタテハの一種(タテハチョウ) ほか)
第5章 ナナフシ・カマキリなど(エウドリラスの一種(アタマアブ)
アコンティスタ・マルチカラー(カマキリ) ほか)
著者等紹介
西田賢司[ニシダケンジ]
1972年、大阪府松原市生まれ。中学卒業後、単身渡米、高校大学と過ごす。生物学を専攻、卒業したのち中央アメリカのコスタリカへ渡る。1998年からコスタリカ大学生物学部で昆虫の生態を研究、修士号を得る。昆虫を見つける目や飼育観察のよさに定評があり、東南アジアやオーストラリア、中南米での調査も依頼され、「探検昆虫学者」として活躍。現在は、世界各国の大学や研究機関から依頼を受け、コスタリカを拠点に昆虫に関連する数々のプロジェクトに携わる(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
bianca
48
TVでよくお見掛けする西田さん。三分の一はツノゼミ。なんと種類の多いことか。イラストでしか見たことがなく、こんなに沢山写真で見られて感激。擬態種の完成度のすごさや、逆に奇抜に目立って不味さをアピールする種など、怖いけどやっぱり見たくなる。写真がメインだが、コラム「虫を食べますか?」が面白い。私は幼少の頃からイナゴは食べていた。しかし誰でも知らず知らず野菜と一緒に何らかの虫は食べちゃっているもの。蛋白源としての昆虫食が注目されているが、気付かぬうちに…くらいが人間にはちょうどいいに同意。うまみとして(笑)2015/02/19
たまきら
29
こちらで出会った方の素敵な感想を読んで。もう写真にうっとり。特にツノゼミのバラエティにはただただ感動しましたが、我が家は毛虫系が好きなのでもう少しあったら嬉しかったかな。イラガや飛び方が想像もつかない蛾の写真に夢中になりました。虫を食べることについてのとまどい文章がほほえましかったです。プスキャタピラーをまとめた本とかでないかなあ…。2021/10/26
Yuka M
11
装丁にひかれて読んでみた。人間の口咽器官は、虫をたべるようにはできていない。という筆者の考えが、虫のからあげがのったケーキのページに述べられている。笑2015/01/14
noko
5
コスタリカに長年住んで、昆虫を日々採取、観察、飼育している西田賢司さんの虫図鑑。写真が多くて、虫の細かい説明は少なめ。ポリシーとして、標本の写真は極力使われていない。死んだ虫を載せるのには、気がすすまないから。というのが良い!虫は生きているからこそ、見れる色があるので、賛同。ツノゼミの種類が豊富で、西田さんのツノゼミ愛が感じられる。コラムの昆虫食も面白い。人間の口は確かに昆虫を食べるのには向いていないというのは、わかる気がする。タイとかで食べたが、どうしても節足部分が歯の間に引っかかり食べにくい。2021/10/20
ばしちゃん
5
ツノゼミがいーっぱいこちらを向いている、みんな仮面ライダーに見える(笑)他にも色んな虫が載ってるのだけど、写真の側に書かれているコメント、特に説明ではなく個人の感想、がかなりツボです!ぷっ!2015/01/10