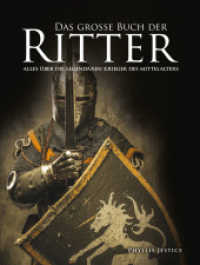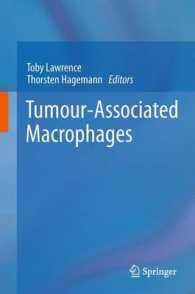内容説明
戦国武将の多くは、嗜みとして美少年(小姓)を寵愛した。主君と肉体関係を結んだ彼らは、忠義の者として重宝され、城主や家宰に出世し、主君の死に殉ずる者もいた。戦国期の主君と小姓の男色は、そのほとんどが江戸期に成立した二次史料を基にしている。また、男色は単なる同性愛ではなく、公家や寺院社会の影響を受けた年長者による少年児童への性愛だった。俗説にまみれた「武家男色」の実相に迫る初めての書。
目次
プロローグ 戦国時代の武家男色、その俗説と実相
第1部 室町幕府と男色文化(公家・宗教社会の男色―禁断の扉を開いた足利義満;足利将軍と男色―稚児から小姓へ;守護大名と男色―大内義隆・武田信玄)
第2部 戦国武将と男色の実相(東国の戦国武将と男色―武田・北条・長尾・今川・朝倉氏ほか;奥州の戦国武将と男色―大崎・上杉・蘆名・蒲生・伊達氏ほか;西国の戦国武将と男色―大内・黒田・宇喜多・毛利・島津氏ほか ほか)
著者等紹介
乃至政彦[ナイシマサヒコ]
1974年香川県高松市生まれ。戦国史研究家。在野の立場から従来説にさまざまな疑問を投げかけ、独自の史観を展開している(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Adoの歌う『踊るポンポコリン』そっくりおじさん・寺
84
こういう内容は大好物である。面白い。男色は「だんしょく」ではなく「なんしょく」と読む。衆道というのも本来「若衆道」。つまり今のゲイとは違い、少年を愛する半ば児童虐待的行為でもあった。室町時代から足利義満が公家や仏教界と交わる様になってから武家に衆道が入ってきた。その過程を史料を引用しながら教えてくれる。武将には男色伝説が多いが、実際は噂に過ぎないものが多いのも検証してあり面白い。男色が必ずしも礼讚に価した時期というのは無い様だ。男色の対象になったばかりに人生を棒に振る者もいた。かなりお勧めです。2014/04/30
春風
18
武家男色とは武士による男児性愛。同性愛とは異なる。戦国期の男色エピソードはいくつか知られているが、それらの典拠となる史料が殆ど江戸期に書かれた事は注目に値する。戦国期の男色は、傾国の因となることが意識され緊張があったため、節度を持って行われたようだ。しかし太平の江戸期に至るとそれは廃れ、単なる児童への性虐待とみなされた。そのような反男色的背景がある中で書かれた戦国武将の男色譚がどのようなものであるかは推して知るべしである。戦国期の男色に特化した類書はなく、有名な逸話を全国的に収録し、検討している良書。2018/08/12
YONDA
17
信長と蘭丸、信玄と高坂など戦国時代の男色としては有名だが真実ではないらしい。お気に入りの小姓と関係を持ち出世させると、家臣からの反発が強まり寝首を掻かれる戦国時代。男色は秘める恋の戦国時代。泰平の世となると秘めなくてもよい恋となり、お触書も頻繁だった。「衆道」と言う言葉は、正当化するための都合の良い言葉。「衆道は武士の嗜み」なんて嘘だったとわかる一冊。2019/08/05
fseigojp
11
この本と 武士道とエロスは併読して比較すべき2015/08/03
金監禾重
7
信憑性の高低を問わず事例を多数紹介(低い事例が煩多)。「武家衆道の盛衰」はよくまとまっていると思う。ただ、著者の資料読解力に疑問。連歌師宗祇が大内氏家臣の陶弘詮に歓待された際の記述「此のあるじ、年廿の程にて、其の様、艶に侍れば、」を「弘詮が、二十歳ほどの艶な若者を侍らせ、」と読んでいる。この「侍れば」は丁寧語で、主語が「此のあるじ」としか読めないはず。Wikipediaを見れば弘詮は生年不明だが、兄弘護が当時数えで26歳なので、弘詮は20歳ほどとなり宗祇の記述と矛盾しない。2024/06/19
-

- 電子書籍
- リリアスアカデミー【タテヨミ】 1話 …