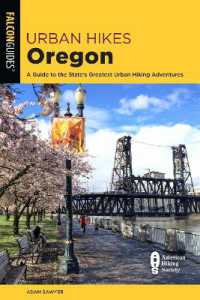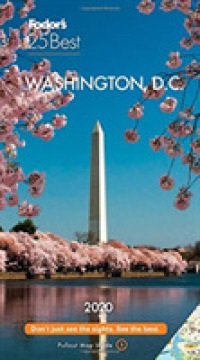内容説明
「宮沢賢治」「わんこそば」「盛岡冷麺」などが連想されがちな岩手県―。しかし、古くはヤマト王権に属さない縄文文化の栄えた土地だった。平安時代末には藤原氏が登場し、黄金文化に彩られた「平泉の世紀」を現出する。南北朝時代以降、南部氏が台頭し、戦国時代末には県域支配を進めた。江戸時代には南部(盛岡)藩と仙台藩の支藩一関藩が安定的な治世を展開。幕末には盛岡藩が東征軍を迎え討って敗れるが、近代に入ると学者や作家・政治家など優秀な人材を輩出し時代をリードする。本書では、魅力あふれる意外な岩手県の歴史を紹介する。
目次
第1章 岩手県の古代(金森遺跡の発掘で分かった岩手県の二万年前の自然環境とは?;岩手県出土の縄文「土偶」で何が分かった? ほか)
第2章 岩手県の平泉・鎌倉・室町時代(藤原清衡はなぜ「平泉」に拠点を置いた?;「柳之御所跡」などの発掘で分かった「平泉」の姿は? ほか)
第3章 岩手県の戦国時代(戦国時代の岩手県域にはどんな国人領主がいた?;県北地域に戦国時代を招いた三戸南部氏・九戸氏とは? ほか)
第4章 岩手県の江戸時代(盛岡城が南部氏の居城となったのはなぜ?;盛岡城下で四百年も続いた商家「十一屋」とは? ほか)
第5章 岩手県の近代(旧幕府軍のアボルダージュ作戦はなぜ失敗した?;岩手県はどのようにして成立した? ほか)
著者等紹介
山本博文[ヤマモトヒロフミ]
1957年、岡山県生まれ。東京大学文学部国史学科卒業。文学博士。東京大学大学院情報学環・史料編纂所教授。専門は近世日本政治・外交史。『江戸お留守居役の日記』(読売新聞社、のち講談社学術文庫)で第40回日本エッセイストクラブ賞を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ちくわん
doublebeko
よし