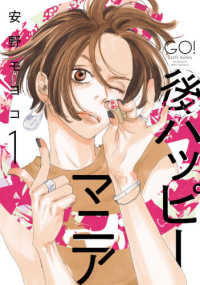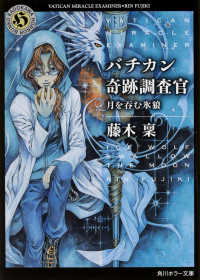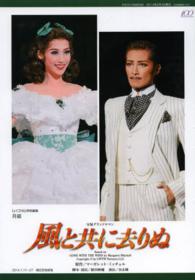出版社内容情報
世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか?』がベストセラーとなっている企業コンサルティングの山口周氏、そして『ストーリーとしての競争戦略』で知られる一橋大学教授・楠木健氏による「新時代の仕事論」をテーマにした対談本。GAFAに太刀打ちできず、海外IT企業に食われるばかりの日本企業。IT分野だけでなく、その他の分野でも日本企業は世界的にイノベーションを起こすこができなくなっている――。日本企業の停滞の原因は、旧態依然とした「仕事ができる」ことへの評価にあった。不安定で不確実、かつ曖昧で複雑化する現代社会では、情報処理スキルには限界があり(誰がやっても同じ答えになる)、2人は「仕事ができる=スキルが高い」というモードから、「仕事ができる=センスがある」といわれる感性、感覚、勘などが重要視される時代にならざるを得ない、と予言する。あなたの仕事観を根底から変える、新時代の仕事の教科書。
内容説明
MBA、論理的思考…デフレ化するビジネススキル。スキルよりセンスがものをいう時代。「論理」と「感性」をめぐる新時代の仕事論。
目次
第1章 スキル優先、センス劣後の理由(アート派、センス派は“ビルの谷間のラーメン屋”;ビジネスとは問題解決 ほか)
第2章 「仕事ができる」とはどういうことか?(労働市場で平均点にお金を払う人はいない;「やってみないとわからない」センスの事後性 ほか)
第3章 何がセンスを殺すのか(ビジネスパーソンの「エネルギー保存の法則」;「横串おじさん」と位置エネルギーの“魔力” ほか)
第4章 センスを磨く(センスの怖さはフィードバックがかからない点;島田紳助の「芸人は努力するな」の意味 ほか)
著者等紹介
楠木建[クスノキケン]
1964年東京都生まれ。89年一橋大学大学院商学研究科修士課程修了。一橋ビジネススクール教授。専攻は競争戦略。企業が持続的な競争優位を構築する論理について研究している
山口周[ヤマグチシュウ]
1970年東京都生まれ。慶應義塾大学文学部哲学科、同大学院文学研究科修士課程修了。独立研究者、著作家、パブリックスピーカー。電通、ボストン・コンサルティング・グループ、コーン・フェリー等で企業戦略策定、文化政策立案、組織開発に従事。現在、株式会社ライプニッツ代表、株式会社中川政七商店、株式会社モバイルファクトリー社外取締役、一橋大学大学院経営管理研究科非常勤講師(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
W-G
みき
Yuma Usui
いーたん
てってけてー