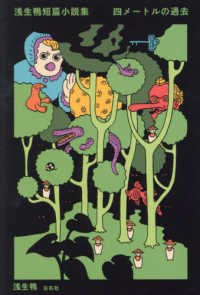出版社内容情報
私はこれまで、薬の役割と薬を飲み続けることのリスクについて、講演会や著書で
何度もお伝えしてきました。
ただ、ひとつ抜け落ちていたと思うのは、薬をどの世代よりも利用する高齢の方々
へ向けた警鐘です。
厚生労働省の調査によれば、75歳以上の約25パーセントが7種類以上、40パーセン
トが5種類以上の薬を処方されているといいます。
「1錠」でも副作用などのリスクがある薬です。何種類も飲む(多剤服用)ことによ
る危険性は想像に難くありません。
飲み合わせによっては、予想もできない副作用が起きることがあるのです。
また、若い人に比べ高齢者の服薬は、ただでさえリスクが高いことをご存じでしょ
うか。
加齢により身体は衰えます。若い時にはなんでもなかったその「1錠」が、大きな
肉体的負担となってしまうのです――。
2018年5月、厚労省は高齢者の多剤服用に関して医師や薬剤師に向けにガイドライ
ンを発表しました(『高齢者の医薬品適正使用の指針』)。
これは、薬による体調不良を起こす高齢者の存在、医療費の増大が背景にあると思
われます。
本書ではこの厚労省のガイドラインに言及しつつ、減薬や薬のない生活を送るため
の方法も提案します。
目次
第一章 薬剤師だけが知っている薬の正体
・私が「薬を使わない薬剤師」になった理由
・生活習慣病は薬で治すことはできない
・私が薬を手放せた理由
・病気を治すのは「自然治癒力」
・インフルエンザでも薬を飲まない
・薬を飲んだときに体内で起きていること
・薬の服用で必要な「酵素」が無駄に使われる
・4剤以上飲まされている患者は「危険な状態」
・「基準値」にとらわれすぎる日本人 ほか
第二章 高齢者が知らない“薬漬け"のリスク
・どうして飲む薬の種類が増えるのか?
・5剤以上飲んでいる人は見直しが必要
・薬は「若い時と同じ」感覚ではダメ
・厚労省が「多剤服用」の危険性に言及
・薬の組み合わせは無限大で把握不可能
・「多剤服用」は皆保険制度の弊害
・相談できる「かかりつけ薬局」を見つける
・「お薬手帳」は必ず一冊にまとめる
・薬剤師とうまくつきあうコツ ほか
第三章 歳を過ぎたら飲んではいけない薬
・不調の原因は「老化」なのか、「薬」なのか
・厚労省が公表した「高齢者が注意すべき薬」
・私が考える高齢者がとくに注意を要する薬
第四章 薬に頼らない生活
・「薬に頼らない生活」をすすめる理由
・「薬を飲んだらどうなるか」を自問自答する
・身体を変えなければ「減薬」は成功しない
・「食事」と「運動」があなたの身体を変える
・疲れたときには「果物」を食べる
・「まるごと」食べれば栄養満点 ほか
内容説明
降圧剤で記憶障害、せん妄のリスク。抗うつ剤の副作用は「うつ」症状。効果より副作用が大きい抗インフル薬。睡眠薬、高コレステロール治療薬、抗不安薬、認知症治療薬などの危険性も。厚労省が専門家のみに注意喚起している「多剤服用」の危険!薬に頼らない生活と減薬のコツも公開。
目次
第1章 薬剤師だけが知っている薬の正体(私が「薬を使わない薬剤師」になった理由;生活習慣病は薬で治すことはできない ほか)
第2章 高齢者が知らない“薬漬け”のリスク(どうして飲む薬の種類が増えるのか?;5剤以上飲んでいる人は見直しが必要 ほか)
第3章 65歳を過ぎたら飲んではいけない薬(不調の原因は「老化」なのか、「薬」なのか;厚労省が公表した「高齢者が注意すべき薬」 ほか)
第4章 薬に頼らない生活(「薬に頼らない生活」をすすめる理由;「薬を飲んだらどうなるか」を自問自答する ほか)
著者等紹介
宇多川久美子[ウダガワクミコ]
1959年、千葉県生まれ。薬剤師・栄養学博士。明治薬科大学卒業後、薬剤師として総合病院に勤務。一般社団法人国際感食協会理事長、ハッピーウォーク主宰(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
nyaoko
マリリン
gtn
乱読家 護る会支持!
fumikaze