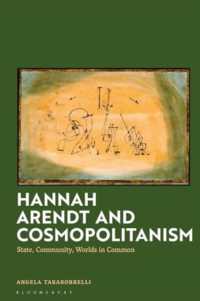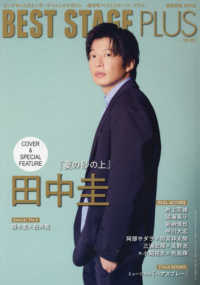内容説明
つながっているのに寂しい、「常時接続の世界」を生き抜くために。哲学という「未知の大地」をめぐる冒険を、ここから始めよう。
目次
第1章 迷うためのフィールドガイド、あるいはゾンビ映画で死なない生き方
第2章 自分の頭で考えないための哲学―天才たちの問題解決を踏まえて考える力
第3章 常時接続で失われた〈孤独〉―スマホ時代の哲学
第4章 孤独と趣味のつくりかた―ネガティヴ・ケイパビリティがもたらす対話
第5章 ハイテンションと多忙で退屈を忘れようとする社会
第6章 快楽的なダルさの裂け目から見える退屈は、自分を変えるシグナル
著者等紹介
谷川嘉浩[タニガワヨシヒロ]
1990年生まれ。哲学者。京都大学大学院人間・環境学研究科博士後期課程修了。博士(人間・環境学)。現在、京都市立芸術大学美術学部デザイン科講師。哲学者ではあるが、メディア論や社会学といった他分野の研究やデザインの実技教育に携わるだけでなく、企業との協働も度々行っている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
R
93
タイトルの通りながら、スマホがもたらしたというよりも、スマホの登場により哲学における孤独の概念の説明がつけやすくなったといった感じだった。孤独の必要性や、解決しないことによる成長みたいな効能めいたものを哲学が余白として提示しているそうで、昨今はそういう余白をスマホによって埋めてしまっているから内省や自己と向き合う力が訓練されづらいという指摘があってなるほどと思う。世代とか関係なく、風潮や流行として、なんでもさくさく白黒つける感じだが、近道をして大きなものを逃しているのかもと思った。2025/10/27
アキ
88
スマホは生活に必需品となったが、常時側にあることによる弊害には中々気付かない。本書は、そんな現代に孤独の価値を説く。哲学とは世界や自分を捉える理論だが、デカルトやニーチェを持ち出されても、西洋哲学とはプラトンに対する一連の注釈から始まると言われる様に日本人である私にはピンと来ないもの。著者は、映画「ドライブ・マイ・カー」や「燃えよ、ドラゴン」「新世紀エヴァンゲリオン」などからの引用で、哲学用語をなるべく用いずに、読者を導いてくれます。「他者の抱く疑問について一緒に考えてみる」という視点が新鮮でした。2025/09/28
konoha
51
最初は哲学の話が難しいなと思ったが、エヴァンゲリオンなどの例えが親しみやすい。エヴァを知っている人ならより楽しめそう。私が新書を読むきっかけになった東畑開人さんの引用も多く、うれしかった。東畑さんの著書と同様、腑に落ちることがたくさんあった。スマホで「快楽的なダルさ」に浸る感覚はわかる。孤独と向き合うこと、趣味を作ることが大事。細切れの時間にスマホを見るのはある程度仕方ないのかなと思う。注釈が細かく、よく読むと大事なことが書かれている。平野啓一郎さんの分人主義を一部批判していたのが印象的。2025/12/18
Book & Travel
43
多くの人が推奨しているだけあり、とても興味深く、心に刺さる一冊だった。スマホにより常時接続された現代。そんな世界でこそ大切なのは、「孤独」と向き合うこと、といっても内に籠るのではなく他者の想像力を取り入れること、モヤモヤをすぐに理解した気にならず心に抱えておくネガティブ・ケイパビリティ、等々。ハンナ・アーレントら哲学者の言葉だけでなく、エヴァンゲリオンや燃えよドラゴン等の例を挙げて述べられ、分かり易く腑に落ちる内容が多かった。とはいえ真髄の部分は簡単では無い所もあり、また時を置いて再読してみたい。2025/11/30
ウォーカー
36
常時接続の時代だからこそ「孤立」と「孤独」を特に大切にし、「モヤモヤ」や「消化しきれなさ」を抱えながらも冒険的な好奇心をもって試行錯誤し、他者性を取り込んだ自己対話を通じて「何かを作り、何かを育てる」こと(著者の言う「趣味」)が大切だと理解した。創作や育成といった創造的な活動が何を意味するのか、何かを知り続けようとすることの意味は何かを考えさせてくれる。スマホ時代に限らず良い生き方のヒントがちりばめられていると感じた。ブルース・リーや「エヴァ」の登場人物のセリフが深掘りされていくプロセスが面白かった。 2025/09/15
-

- 電子書籍
- 恋の道に迷ったら【分冊】 11巻 ハー…