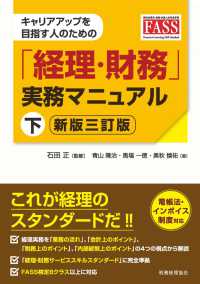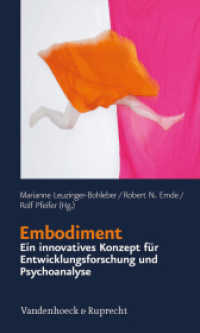内容説明
“軍事的な世界観”を抜け出せない組織は、どんどん弱体化し、人が逃げていく―。“冒険的な世界観”をインストールし、「人が集まる会社」「本当に強いチーム」をつくるには?
目次
序論 “冒険する組織”とはなにか?―「軍事的世界観」からの脱却
第1部 理論編 冒険する組織の考え方(会社の「世界観」を変える―5つの冒険的レンズ;自己実現をあきらめない「冒険の羅針盤」―新時代の組織モデル;冒険する組織をつくる「5つの基本原則」)
第2部 実践編 新時代の組織をつくる「20のカギ」(冒険する「目標設定」のカギ;冒険する「チームづくり」のカギ;冒険する「対話の場づくり」のカギ;冒険する「学習文化づくり」のカギ;冒険する「組織変革」のカギ)
著者等紹介
安斎勇樹[アンザイユウキ]
株式会社MIMIGURI代表取締役Co‐CEO。1985年生まれ。東京都出身。東京大学工学部卒業、東京大学大学院学際情報学府博士課程修了。博士(学際情報学)。組織づくりを得意領域とする経営コンサルティングファーム「MIMIGURI(ミミグリ)」を創業。資生堂、シチズン、京セラ、三菱電機、キッコーマン、竹中工務店、東急などの大企業から、マネーフォワード、SmartHR、LayerX、ANYCOLORなどのベンチャー企業に至るまで、計350社以上の組織づくりを支援。また、文部科学省認定の研究機関として、学術的成果と現場の実践を架橋させながら、人と組織の創造性を高める「知の開発」にも力を入れている。ウェブメディア「CULTIBASE」編集長。東京大学大学院情報学環客員研究員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
T2y@
ta_chanko
はる坊
江口 浩平@教育委員会
小泉岳人