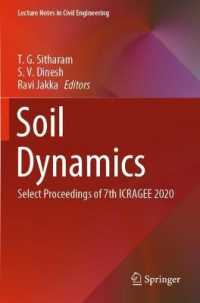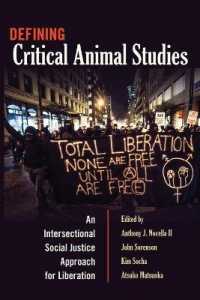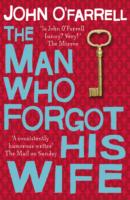内容説明
世界で通用するT型キャリアのつくり方。
目次
1章 人生100年時代は「飛び出す人」がキャリアを築く
2章 外に飛び出すことで、手に入る「もの」
3章 思い込みの外に飛び出す
4章 業界の外に飛び出す
5章 作られた枠の概念から飛び出す
著者等紹介
坪田一男[ツボタカズオ]
株式会社坪田ラボ代表取締役CEO/慶應義塾大学名誉教授/慶應義塾大学医学部発ベンチャー協議会代表/医学博士/経営学修士(MBA)。1980年、慶應義塾大学医学部を卒業し、医師免許取得と共に同学部眼科学教室に入局。87年、米国医師免許を取得し、ハーバード大学角膜クリニカルフェローを修了した。東京歯科大学眼科を経て、2004年から2021年まで慶應義塾大学医学部眼科学教室教授。研究面ではドライアイや近視の領域で多数の論文を発表。発表した論文の数とその被引用数をベースに研究者のその分野への貢献度を示すh-index(h指数)は125を超え、医学分野で国内トップクラスに位置する。教育面では慶應義塾大学医学部の「Best Teacher Award」を3度受賞した。15年、株式会社坪田ラボを創業し、22年東京証券取引所グロース市場に上場させた。現在も経営者、そして研究者として継続してドライアイ、近視、老眼の課題解決のための研究、開発を行っている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ニッポニア
70
疑わずに最初の一段を登りなさい、階段の全てが見えなくてもいい、とにかく最初の一歩を踏み出す。インプットの対としてアウトプットを。物事を深く知る、深化だけでは到達できない領域があり、そこにいくためのゴーアウト。つまり深化を促進させるためには、与えられたシステムだけでなく、ゴーアウトによる「自力の学び」が必要。余白を持つことで、思考が広がる。本来ブルーライトは脳を活性化する重要な光だった、現在では溢れすぎて安回らない状況に。ゴーアウトは脳にとっても重要な行動。パーティーはコミュニケーションを深める重要な手段。2024/03/23
とある内科医
20
推しの教授による本なので、無条件に購入(気付くのは遅れましたが…)。著者とは別の領域で医師をしており、まさにゴーアウトして直接お会いしに行ったことが何度かあります。これまでに聞いた講演の中でもダントツで心に響き、強烈な印象を受けました。本書も同様、自分なりに世界一を目指すためのヒントと刺激を大いに頂きました。 ハーバード大留学×慶大教授×日米医師免許×MBA×スタートアップ上場企業社長、という帯。あれ、MBA持ってらっしゃった⁉︎、と思いながら読み進めると大学教授をしながら62歳での入学!2024/05/25
かいてぃ〜
16
GO OUT→ 「コンフォートゾーンから出て、新たな世界を覗くこと」。そこで学びを得られれば良いが、必ずしも学びを得られなくても問題は無いそうです。まずは探索することが大事で、現状維持はやはり退化なのだろう。仕事で役立ちそうなものを探して触れてみるのも良いし、全く仕事に関係ないものも興味があれば触れてみるのも良いし、色々と探してみるかな。2023/11/19
ロクシェ
15
評価【◎゚】本書のタイトルGO OUT(ゴーアウト)には、「家の外へ飛び出すこと」と「専門外の領域へ飛び出すこと」という2つの意味が込められています。医学博士(眼科学)でもあり、株式会社の代表取締役でもあり、慶應義塾大学の名誉教授でもある著者は、プロフィールからはとても想像できませんが、爽やかでポジティブなナンパ師。たとえば読んだ本や論文に感銘を受ければ、男女問わず、国内・国外問わず、まったく何の面識がない状態でもアポを取り、書いた人に会いにいくそうです。ふつう、眼科医が書いた本なら眼科の話が中心になり↓2023/05/16
おの
13
PrimeReadingにて。いまだにこういうタイトルにホイホイされてしまう。いきなり「私は本を200冊読みます」から始まり嫌な予感はしていたが、それらしいことをそれらしく言っていきなり近視の話になったので途中下車。素直な若者にはいい本なのかもしれない。いい加減お菓子本読むのやめようと自分に誓った←2024/07/02