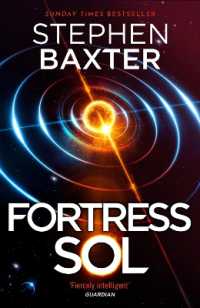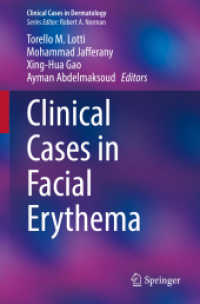- ホーム
- > 和書
- > ビジネス
- > 仕事の技術
- > 話し方・コミュニケーション
出版社内容情報

「ディスカヴァー・トゥエンティワン」のnoteでは、
各書籍の担当編集者による、熱い「推しポイント」をご紹介しています。
こちらからご覧ください!(外部サイトに遷移します。)
⇒問いかけの作法―チームの魅力と才能を引き出す技術
内容説明
問いかけの作法とは、チームメンバーの魅力と才能を引き出し、チームのポテンシャルを最大限に発揮するための誰にでも習得可能な技術です。問いかけの技術を駆使することで、「他力」を引き出し、一人では生み出せないパフォーマンスを生み出すこと。これが、現代の最も必要なスキルの一つなのです。
目次
1 基礎編(チームの問題はなぜ起きるのか;問いかけのメカニズムとルール)
2 実践編(問いかけの作法1 見立てる;問いかけの作法2 組み立てる;問いかけの作法3 投げかける)
著者等紹介
安斎勇樹[アンザイユウキ]
株式会社MIMIGURI代表取締役Co‐CEO。東京大学大学院情報学環特任助教。1985年生まれ。東京都出身。東京大学工学部卒業、東京大学大学院学際情報学府博士課程修了。博士(学際情報学)。研究と実践を架橋させながら、人と組織の創造性を高めるファシリテーションの方法論について研究している。ファシリテーションを総合的に学ぶためのウェブメディア「CULTIBASE」編集長を務める(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
けんとまん1007
73
いい問いは、いい答えを導き出すものというのは、自分の中に信念としてある。「問いのデザイン」を読み、関連する本にも触れ、少しずつではあるが実践していると思う。今度は、折角の問いも、問いかけのしかた一つで波及するものが大きく違うということを再認識。それは、作法というレベルのものというのを納得した。ちょうど、中原先生の「話し合いの作法」を読んだこともあり、通底するものを感じる。事前に、場をデザインし、観察しながら場に臨む。その時に、自分自身の傾向も忘れないようにする。いいタイミングで出合えたことに感謝。2023/02/25
ニッポニア
36
問いかけ、という視点からチーム形成、成果へつなげる方法。決してそれだけが全てじゃないけれど、物事は転がり出すきっかけになるもの。問いかけにも「質」の概念を持つこと、思いつきで問いかけるのではなく、入念に用意しておくのも有効です。以下メモ。普段使わない筋肉や関節が固まると体を最大限に使うことができなくなる。作業の目的を感じられなくなっても、手段そのものを続けるのに没頭するのも環境適応。良い問いかけとは、味方を生かすパス。どのような第一声で注意を引くか、最初の5分が勝負。余白を演出する。2022/08/06
黒縁メガネ
16
質問に対しての回答が求めていたものも違って、話が食い違うなんてことがたまにあります。質問に対しての回答が悪いばかりではなくて、問いかけに問題が無いか考えるきっかけになりました。2022/09/02
練りようかん
14
『問いのデザイン〜』が面白かったので二冊目。チームミーティングでポテンシャルを活かした質の高いアウトプットを目指し、問いかけを見直すと「見えない前提」が見えてくるのが楽しい。悪循環から抜け出す四つの技術ではパラフレイズが気になり、通読の間座標軸設定の大切さを痛感していたのだが、まとめの共通言語の再定義に戻りこれも発散と収束なのかとハッとした。心理学と経営学の理論を照らし合わせながら解析で、特に心を射止めたのは緩叙法の“検討できるボツネタありますか?”だ。ハードル下げ&具体的で良い、いつか使いたい。2025/10/20
bookreviews
13
問いかけは大事ではありますが、単に問いかければいいというものではありません。 意見が出ないときによくやってしまいがちな、「無茶ぶり」「不意打ち」はよい問いかけではないことはよく理解できました。また、愛着が溢れる「こだわり」や、形骸化しつつある「とらわれ」という言葉や考え方も、絶妙な表現だと思います。 https://bookreviews.hatenadiary.com/entry/MannersOfQuestion2024/02/24
-
- 洋書
- Fortress Sol