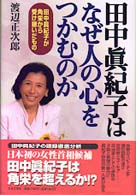内容説明
ものごとは、変化し、生まれては滅ぶ。そのあやうさをおそれる必要はない。それどころか、あなた自身が、可能性に満ちたものとしてあることを理解すれば、あなたは、わけのわからぬ不安から解放される。「東大話法」批判の著者が五年の歳月をかけて取り組んだ渾身の『老子』新訳!
目次
ものごとは常に変化する。あなた自身もそうだ。
言葉に縛りつけられるな。言葉を縛りつけるな。
確かなものにすがろうとするから不安になる。あやうさを生きよ。
あやうい状態からこの豊かな世界が生まれた。
この世界にはもともと、善悪も優劣もない。
言葉で世界を切り分けようとするな。
支配者が頭を回さなければ、うまく治まる。
「道」とは、ものごとを成り立たせる不可思議な力。
よく生きるには、感性を豊かにすればよい。
自らの内なる声に従え。〔ほか〕
著者等紹介
安冨歩[ヤストミアユミ]
あゆむ、も可。東京大学東洋文化研究所教授。1963年生まれ。京都大学経済学部卒業後、株式会社住友銀行勤務。京都大学大学院経済学研究科修士課程修了。京都大学人文科学研究所助手、名古屋大学情報文化学部助教授、東京大学大学院総合文化研究科・情報学環助教授を経て現職(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
壱萬参仟縁
27
生きるためには、ものごとの根源に立ち返り、自らを、そのあやうさに委ねればよい(022-3頁)。人がよく生きるには、感性を豊かにすればよい(036頁)。ありのままの世界を知れば、寛容になる。寛容であれば、公平になる。公平であれば、王たるにふさわしい(071頁)。柔らかく弱いものが強いものに勝つ(120頁)。物は威勢が良すぎると衰える。不自然な生き方をすると、早く死んでしまう(168頁)。超訳といえる。2021/03/18
wiki
19
超訳というものを初めて読む。平易に書いているようであって、その中身はモヤっとしたモノを直接の呼び名無くモヤっと感覚的に伝えようとしている感じで、何とも捉え難く、理解し難い。"道"と仮称され、安冨氏に"存在"と仮称された"それ自体"とは、一体何か。そこをガシッと捕まえられない。名前がつけられると名前のハコに入ってしまい、"それ自体"でなくなってしまうというのもあるだろうが、"それ自体"が掴み所なくては、伝えようもない。そうした意味では、真理につけた名前というものが大事で、名付けるということは尚大事だと思う。2019/02/27
hatman
11
抽象概念で人の道を説いた哲学書。 美醜善悪などの比較は人が作り出している。何事も人が作り出した価値観で比較するので生きづらくなる。手に入れたら離したくない、成果をあげたら主張したい。刺激を得て本当の問題から目を背けて、目を背けている事実からも目を背ける。 水の流れのように自然体で、謙虚に、わかったつもりにならずに、後から効いてくる様な人になるのがベターなのかな。2024/02/12
スナフキン
8
老子の超訳。私には難しかった。 老子には様々な原本があり、解釈も多様であることを初めて知った。 無為を是とする老子の考え方は好きなので、腹落ちするまで繰り返し読みたいと思った。 東洋哲学の深さを味わえる一冊。 2020/10/07
らる
6
何かにおびえているとしたら、それは、自身が作り出した名におびえているだけ。言葉の意味は常に生まれては消えている。どうなるかわからない開かれたもの。そこを理解すれば意味の分からぬ不安から解放される/感性を豊かにする。身体を通じて物事を感じる。自分がどうすればよいか、ただちにわかる。/最高の善は水。万物に利益を与え、静かであり、多くの人が嫌がる低い場所にいる/言葉のない教え、無為の有益さに、匹敵しうるものは天下にない/威勢が良すぎると衰える/ものごとを知るためには、言葉に頼るのをやめねばならない2021/07/23
-
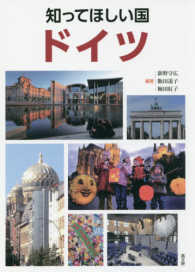
- 和書
- 知ってほしい国ドイツ