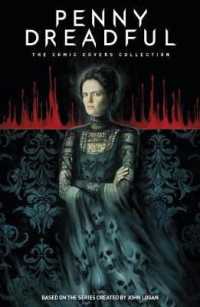出版社内容情報
チャンスは1970年1月、カリフォルニア大学バークレー校で数学を専攻した大学院1年目におとずれた。……新年度を迎えて一般相対論としばしばよばれる理論の講義を聴講しはじめた。そこで引力として長らく説明されてきた重力が、より正確には幾何学的な効果で、巨大な物体の存在による時空の湾曲または歪みの結果と知り、驚いた。これは私にとって、ある種の啓示のようなものだった。物理学が幾何学とこれほど密接に関係しているとは、まったく気づいていなかったからだ。 (シン=トゥン・ヤウによる「はじめに」より)
じつのところ一般相対性理論が実り多きものである証の一つは、一般相対性理論が発表されて1世紀以上たった現在も、物理学者や数学者がその意味を解明しようと理論の新たな一面を見つけては押したり突いたりと探求をつづけている事実だ。この大成功を収めた生産的な理論が、半世紀近くにわたり物理学者からほとんど無視されていた幾何学という数学の一分野を中心にして構築されたことは忘れてはならない。……もちろんこれは数学の驚異的な持続力を物語ってもいる。厳密に証明された数学の定理は、人類史上ほかに類を見ないとはいわないまでも、つねに維持されるという稀有な性質をもっている。……これらの〈公理〉は、ある種のツールであり、その後たとえ数世紀たったとしても再発見されて、もとの考案者が夢にも思わなかったような方法で利用されうるということだ。1900年代初頭に起きた、まさにこの種の「リサイクル」行為こそが、本書の著者二人が語りたい物語の中心にあるものだ。 (前奏曲「円錐の切り方は一つじゃない」より)
一般相対性理論の〈場の方程式〉の導出は、こんにちにおいても称賛にあたいする記念碑的な偉業だった。ところがアルベルト・アインシュタインはその勝利の瞬間においてさえ、みずから苦労して考えだした連立非線型偏微分方程式の厳密解を見つけられるか否かに確信がもてず、ほかの人が提示した解のいくつかに対しても懐疑的なままだった。……物理学者ブランドン・カーターは次のように書いている。「アインシュタインの仕事は革命的な意味をもっていたが……彼の本能はむしろ保守的な傾向があった」。 (第4章「特異すぎる解」冒頭より)
内容説明
ニュートンの“古典力学”からアインシュタインの“相対性理論”さらには“量子重力理論”という今後期待される“統一理論”まで。世紀を超えた重力論/宇宙論の躍動・発展のあゆみを一気に概観!
目次
前奏曲 円錐の切り方は一つじゃない
第1章 落下する物体、移り変わるパラダイム
第2章 「一般」へ至る道すじ
第3章 最高傑作
第4章 特異すぎる解
第5章 その波を追いかけて
第6章 全宇宙の方程式
第7章 質量問題という問題のかたまり
第8章 「統一」への探求
後奏曲 真のミステリースポットはどこにある?
著者等紹介
ネイディス,スティーヴ[ネイディス,スティーヴ] [Nadis,Steve]
サイエンス・ライター。米国マサチューセッツ州ケンブリッジ在住。ハンプシャー・カレッジ卒。米国の著名な科学誌“Discover”で寄稿編集者、同じく米国の科学誌“Quanta”のライターをつとめる
シン=トゥン・ヤウ[シントゥンヤウ]
丘成桐。中国・広東省汕頭市生まれ。香港中文大学卒業後に渡米。カリフォルニア大学バークレー校で学び、1971年に博士号取得。1990年、米国籍取得。ハーヴァード大学名誉教授。現在は北京在住で、2022年より清華大学で数学主任教授。時空の余剰次元を6次元とする「カラビ=ヤウ多様体」の生みの親として宇宙論の分野で名を知られ、数学に関する賞の最高権威「フィールズ賞」を1982年に受賞。また、アインシュタインの友人で同級生だったスイスの数学者グロスマン(本書にも登場)の名を冠した「マルセル・グロスマン賞」を2018年に受賞した
辻川信二[ツジカワシンジ]
早稲田大学先進理工学部物理学科教授。専攻は一般相対性理論、宇宙論。博士(理学)。東京大学理学部数学科卒業後、早稲田大学大学院理工学研究科で宇宙物理学を専攻。2001年、同研究科で博士後期課程修了。2003年、英国ポーツマス大学Institute of Cosmology and Gravitationに研究員として滞在。2004年に帰国し、群馬工業高等専門学校講師、東京理科大学准教授、同教授をへて、2020年より現職(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
やいっち
やいっち
やいっち
やいっち
薫風