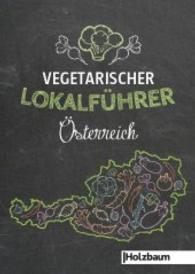- ホーム
- > 和書
- > 経営
- > 経営管理
- > ナレッジマネジメント
出版社内容情報
安藤広大[アンドウコウダイ]
内容説明
「話のわかる上司」「いい社長」こそが組織をダメにする!?組織パフォーマンスを最大化するマネジメント手法。
目次
0 序章 組織は誤解や錯覚に満ちている
1 社長は現場に近すぎてはいけない!―伸びる会社の社長の役割
2 社長は部下の「がんばっている姿」をほめてはいけない!―伸びる会社の評価基準
3 社長は部下から上司の評価を聞いてはいけない!―伸びる会社の組織づくり&組織運営
4 社長は部下の「やり方」に口を出してはいけない!―伸びる会社のマネジメントルール
5 会社に合わせることができない人材を雇い続けてはいけない!―伸びる会社の人材採用&育成
6 社長は部下と二次会に行ってはいけない!―伸び続ける会社の社長の行動ルール
著者等紹介
安藤広大[アンドウコウダイ]
1979年、大阪府生まれ。1998年大阪府立北野高等学校卒業。2002年、早稲田大学卒業。株式会社NTTドコモを経て、2006年にジェイコムホールディングス株式会社(現:ライク株式会社)に入社。主要子会社のジェイコム株式会社(現:ライクスタッフィング株式会社)で、取締役営業副本部長などを歴任。2013年、「識学」と出会い独立。識学講師として、数々の企業の業績アップに寄与する。2015年、識学を1日でも早く社会に広めるために、株式会社識学を設立(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
W-G
285
バッサリと独善的に言い切る論調のせいもあってか、他の人のレビューでも懐疑的な意見が多い。ただ、刺さる言葉も割と多く「モチベーションを上げようと頑張ると、モチベーションが上がらないと頑張らなくていいと誤解」「ストレスがない=成長がない」などは職場あるある。こういう本は”リーダー”の定義が曖昧なせいで自分に照らし合わせるのが難しくなるものも多い。コレも”リーダー=社長/経営者”のためのものなので、例えば部課長レベルで鵜呑みにすると痛い目を見る項目もあるので注意が必要かと。2018/05/28
Yuma Usui
32
主に社長や管理職向けにすべき事とすべきでない事がまとめられている。社員のモチベーションや仕事のプロセスなどを敢えて無視して、ただ結果のみで社員を評価することで業績向上を図る方法を教えてくれる。業績につながるルールと評価指標を精度良く作れるか否かが鍵と感じた。社員数が増えてルールベースで業務を回す必要が出てきたときに参考になりそう。2020/12/01
Kentaro
29
組織運営に苦慮し、誤解や錯覚を多く発生させている会社の社長には、実は、「一人の人間として社員から好かれたい。人気者でいたい」という特徴がある。社員から好かれるために、社員の要望にできるだけ耳を傾け、社員が喜ぶようなイベントをたくさん開き、そして、一人ひとりの社員に寄り添い、それぞれの悩みを社長みずから聞くのです。その際の大義名分は、「この対応が会社の成長につながる」ということでしょう。しかし、どこかで、「一人の人間として社員から好かれたい。人気者でいたい」という思いが、判断を狂わせてしまうことがある。2019/03/04
hiro-yo
16
社長への指南書。今の慣例に逆行するタイトルが並んでいるように見えるが、書かれていることは至って当然のことです。「社員に愛社精神を期待するのをやめる」「経営理念を社員全員に理解させるのをやめる」「社員のモチベーションに気を配るのをやめる」「過程プロセスを評価することやめる」など。2019/04/19
あつお
15
伸びる会社の明確なルール。 アットホームな人間味のある会社が評価されるが、業績を伸ばすには逆を求める必要がある。本書の主な内容は①上司と部下の距離感、②成果を評価、③会社への適応。①上司が会社の飲み会に参加するなど、親睦を深めるのは程々に。上下関係を見失い、客観的な評価・指示が難しくなる。②プロセスではなく、純粋に成績を評価する。そうして初めて、改善点が見える。③社外からの転職者を、評価者として置いてはいけない。一刻も早く自社の文化・ルールに馴染んでもらうのが最適。 自分を能力で評価する癖をつけたい。2023/05/27