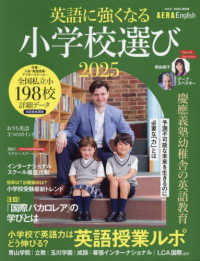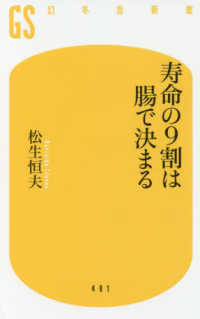内容説明
「私には個人の意見というようなものはない」―では、彼女の言葉はどこからやって来たのか。「池田晶子」とは、いったい何者か。突然現われて去った孤高の思索者の、言葉と存在の謎に迫る。
目次
第1章 孤独な思索者
第2章 月を指す指
第3章 哲学が生まれるとき
第4章 絶句の息遣い
第5章 言葉と宇宙
第6章 常識と信仰
第7章 思い出すということ
第8章 内語の秘密
第9章 「私」とは考える精神である
第10章 夢の向こう
第11章 言葉はそれ自体が価値である
著者等紹介
若松英輔[ワカマツエイスケ]
1968年生まれ。慶應義塾大学文学部仏文科卒業。批評家。「越知保夫とその時代」で第14回三田文学新人賞受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 2件/全2件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Gotoran
47
『14歳からの哲学』の著者で、自分の直観的な結論を読者に唐突に提示しするという独特のスタイルを有する哲学者池田晶子が遺した言葉を手掛かりに、文学・哲学・宗教を縦横に引きながら、人を根源から生かすコトバを探究し、言葉を魂の交わりのコトバに変えることで、人間の救いを浮き彫りにしていく。「私が言葉を語っているのではなく、言葉が私を語っているのだ」と述べる池田。著者の若松は、それを更に存在の深みへと掘り下げていく。難しい内容であったが、非常に興味深かった。著者の池田晶子論に興味深々。再読必須本。2015/11/09
しょうじ@創作「熾火」執筆中。
25
「不滅の哲学」という表題からは、得てして池田の哲学が不滅の価値をもつもの、という意味を読みとってしまうと思うのだが、そうではなかった。著者の若松さんは、池田のコトバを引いて、コトバ、存在、魂の永遠にして不滅の相を解き明かそうとしていた。いわば、「不滅」そのものを表現しようとしていたのではないか。ある曲のタイトルのような「滅せざるもの」や、「破壊され得ぬもの」として表記しようとした軌跡である。希有の書といってもいい。2016/12/05
no.ma
17
言葉の本当の意味を知っている二人の波長はぴったり合っています。哲学の巫女、池田晶子の言葉を引用し、若松英輔は彼女が憑依したかのように語り部となります。そして、読者が読むことによって、その言葉は輝く石となり、やがて賢者の石となります。―― 近代が作り出したもっとも大きなドクサ(臆見)、それが死である。超越と我々は、一即多、多即一の関係。人間が言葉を話しているのではない。言葉が人間によって話しているのだ。―― 私の人生の謎を解く思索はまだまだ続きます。2024/09/09
里愛乍
16
自分が言葉を書くのではない。言葉が自分を用いるのである。「人間とは言葉に用いられる器である」とまで言い切る池田さんはどの本を読んでも〝言葉〟に対する思慕というか執着が凄まじくて、迂闊に「分かる」なんて公言する事など怖くてできない。だけど仰っていることは分かる。私が分かっているのである。若松さんと私の池田さんがイコールかどうかは分からないけど、読んで共感するところがかなりあり、自分の中の池田さんを再確認することができました。2014/06/29
kiho
15
思考の人、池田晶子さんのことはそれほど知らなかったものの、その文章から圧倒的なパワーというか凛としたものを感じた⭐すべてを理解できてはいないけど、考えるという行為のそこはかとない深さを実感!2015/06/09
-

- DVD
- アヴェ・マリアのガンマン