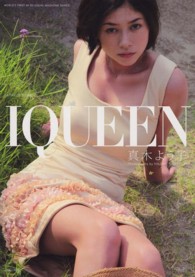出版社内容情報
2018年美術展覧会「入場者数」1位・2位を達成した秘密がここにある
美術館でインスタグラマーが写真を撮り投稿する「#empty」という試みが普及しています。
日本では、2017年4月森美術館が「N・S・ハルシャ展」ではじめて実施し話題を集めました。
今では様々な日本の美術館でアートのシェアが一般化しつつあります。
森美術館は2018年美術展覧会「入場者数」1位・2位を達成しました。
その背景には、日本の美術館・博物館の中で最大規模のSNSフォロワー数を活用したデジタルマーケティング戦略があります。
本書では、森美術館がこれまで取り組んできた展覧会におけるさまざまなSNSの取り組みを紹介しています。
現代アートにおけるプロモーションの最前線を知っていただきながら、
アートとSNSの相性のこと、多少の失敗談など、楽しみながら読んでもらえる内容になっています。
目次
イントロダクション 「レアンドロ・エルリッヒ展」成功の舞台裏
第1章 「撮影OK」の波がアートを変える
第2章 海外の美術館の最新SNS事情
第3章 森美術館のユニークなSNS運用例
第4章 「森美術館流」インスタ&ツイッター活用術
第5章 テクニックよりはるかに大切なこと
内容説明
森美術館は2018年美術展覧会「入場者数」1位・2位を達成しました。その背景には、日本の美術館・博物館の中で最大規模のSNSフォロワー数を活用したデジタルマーケティング戦略があります。本書では、森美術館がこれまで取り組んできた展覧会におけるさまざまなSNSの取り組みを紹介しています。現代アートにおけるプロモーションの最前線を知っていただきながら、アートとSNSの相性のこと、多少の失敗談など、楽しみながら読んでもらえる内容になっています。
目次
イントロダクション 「レアンドロ・エルリッヒ展」成功の舞台裏
第1章 「撮影OK」の波がアートを変える
第2章 海外の美術館の最新SNS事情
第3章 森美術館のユニークなSNS運用例
第4章 「森美術館流」インスタ&ツイッター活用術
第5章 テクニックよりはるかに大切なこと
著者等紹介
洞田貫晋一朗[ドウダヌキシンイチロウ]
森ビル株式会社森アーツセンター森美術館マーケティンググループ広報・プロモーション担当シニアエキスパート。1979年生まれ。東京都出身。2006年森ビル株式会社入社。六本木ヒルズ展望台東京シティビュー、森アーツセンターギャラリーの企画・運営、広報などを経て、現在は森美術館のマーケティンググループに所属。美術館デジタルマーケティング、プロモーションに従事。文化施設におけるSNSの運用についてセミナー講演も多数(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ゆ
山のトンネル
tomosaku
T M
66 (Audible オーディブル毎日聴いてます)