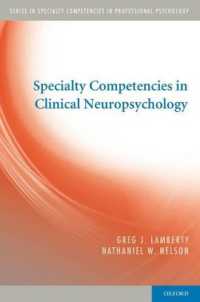出版社内容情報
塹壕線を打開するために生まれたのが戦車であり、その運用方法が「機動の理論」です。本書では、陸上自衛隊で第71戦車連隊長、陸将補を務めた著者が、豊富な図版やイラスト、写真を用いて「機動の理論」の本質を解説します。
第一次大戦では、連合軍もドイツ軍も正面突撃に固執して膨大な死傷者を出し、塹壕線が長期に及びました。これを打開するために生まれたのが戦車であり、その運用方法が「機動の理論」です。機動の理論は英陸軍将校J.F.C.フラーが生み出し、第二次世界大戦のドイツ軍、ソ連軍が確立し、イスラエル軍、米陸軍、米海兵隊が発展させ、現代に受け継がれています。本書では、陸上自衛隊で第71戦車連隊長、陸将補を務めた著者が、豊富な図版やイラスト、写真を用いて「機動の理論」の本質を解説します。
内容説明
第1次大戦では、連合軍もドイツ軍も正面から突破に固執して膨大な死傷者を出し、塹壕戦が長期に及びました。これを打開するために生まれたのが戦車で、その運用方法が「機動戦理論」です。機動戦理論は英陸軍退役将校J.F.C.フラーが生み出し、第2次大戦でドイツ軍、ソ連軍が確立し、大戦後にイスラエル軍、米陸軍、米海兵隊が発展させ、現代に受け継がれています。本書では、陸上自衛隊で第71戦車連隊長、陸将補を務めた著者が、豊富な図版やイラスト、写真を用いて機動戦理論の本質を解説。
目次
第1章 Plan 1919(幻の「Plan 1919」―敵司令部を攻撃して、指揮系統を麻痺させる;J.F.C.フラーと戦車―フラーは歩兵将校で、戦車とは無縁だった ほか)
第2章 幻の野外要務令(幻のマニュアル1 スイスの山荘で速記者に口述した;幻のマニュアル2 英国や米国では無視された ほか)
第3章 実戦へ適用された機動戦理論(電撃戦の衝撃1 ハインツ・グデーリアン将軍;電撃戦の衝撃2 ドイツ国防軍機甲師団の誕生 ほか)
第4章 現代に生きる機動戦理論(機動戦理論の継承―フラーの理論は現代も生きている;イスラエル国防軍(IDF)1 負けることが許されない宿命の国家 ほか)
第5章 「戦いの原則」の創始者(ナポレオンの戦いを分析したフラー―「戦いの原則」制定の経緯1;『野外要務令』に採用された8原則―「戦いの原則」制定の経緯2 ほか)
著者等紹介
木元寛明[キモトヒロアキ]
1945年、広島県生まれ。1968年、防衛大学校(12期)卒業後、陸上自衛隊入隊。以降、第2戦車大隊長、第71戦車連隊長、富士学校機甲科部副部長、幹部学校主任研究開発官などを歴任して2000年に退官(陸将補)。退官後はセコム株式会社研修部で勤務。2008年以降は軍事史研究に専念(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Tenouji
文章で飯を食う
朧月
ソノダケン
泥岳