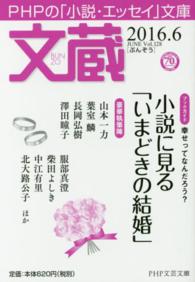出版社内容情報
漢方薬は、速効性のある科学的な薬だった!
東洋思想に縛られず、西洋薬と同じように処方するのが「サイエンス漢方」のキモ! 西洋薬と同じように症状によって合理的に処方する独自の方式が、従来の漢方の概念を覆す。西洋医学が難渋する疾患を抱える人にも、すみやかに解決できる道筋を提起する!
第1章 漢方薬は速効性のある科学的な薬だった<br>
漢方薬は昔から急性期の薬だった<br>
西洋薬の利点と落とし穴<br>
西洋薬との併用で肺炎もすみやかに改善<br>
観念的な東洋思想は後付けされたもの<br>
漢方医療を取り巻く閉鎖的な状況<br>
東洋思想を切り捨てることで漢方は飛躍する<br>
サイエンス漢方処方という考え方<br>
少しずつ漢方薬の謎が解けてきた<br>
西洋のハーブ療法と漢方薬はここが違う<br>
漢方薬は「超多成分系薬剤」と考える<br>
多成分で体の「治す力」を一気に底上げする<br>
患者さんは「自分が治す」という意識をもつ<br>
初期に大量投与するのがポイント<br>
いま体に起こっている不具合に間髪入れずに投与<br>
漢方が欧米で評価されない理由<br>
アメリカで漢方薬の臨床試験が始まった! <br>
<br>
第2章 漢方薬の速効性を支える3つの柱<br>
速効性のしくみ?@ 免疫力を高め、過剰な炎症を抑える<br>
体の「治す力」を迅速に立ち上げる<br>
漢方薬は免疫をいち早く立ち上げる<br>
過剰な炎症を鎮め、障害された組織も修復<br>
西洋薬の穴埋めとして漢方薬は最高の武器に<br>
効果を得るには「炎症の見極め」が重要<br>
風邪に使う薬はどれも免疫賦活・抗炎症作用が高い<br>
漢方薬の刺激で体が自らバランスを回復していく<br>
速効性のしくみ?A 微小循環障害を改善する<br>
微小循環障害は炎症に付随しやすい<br>
さまざまな病気の引き金となる<br>
血管壁での一酸化窒素の産生を促す<br>
心臓外科の分野からも注目されている<br>
速効性のしくみ?B 体内の水分をピンポイントで調整<br>
漢方薬は特定のアクアポリンに作用する<br>
「脳浮腫に五苓散」は脳外科では常識に<br>
膝にたまっている水も漢方薬で解消した<br>
<br>
第3章 急性の病気にここまで効く<br>
日常的に起こりやすい病気<br>
頭痛―タイプによって葛根湯、呉茱萸湯、五苓散を使い分ける<br>
花粉症、アレルギー性鼻炎―中程度までは小青竜湯、重症なら+越婢加朮湯<br>
膝から下のむくみ―猪苓湯または越婢加朮湯
セキ止め―症状に応じた漢方薬を<br>
過敏性腸症候群―下痢型には半夏瀉心湯<br>
貧血―当帰芍薬散<br>
足腰の衰えによるふらつき―八味地黄丸<br>
鼻涙管狭窄で涙が止まらない―紫蘇飲<br>
打撲傷―通導散<br>
筋肉痛―麻杏.甘湯<br>
すぐ治したい不快な症状<br>
こむら返り―芍薬甘草湯<br>
肩こり―葛根湯または桂枝加葛根湯<br>
食べすぎ―六君子湯<br>
鼻血―三黄瀉心湯<br>
いぼ痔―芍薬甘草湯<br>
病院で必ず診てもらう必要のある病気<br>
インフルエンザ―症状の変化に応じて処方<br>
ノロウイルスによる激しい胃腸炎―桂枝人参湯<br>
抗がん剤や首への放射線治療後の口腔粘膜炎―半夏瀉心湯<br>
急性肺炎―小柴胡湯、竹.温胆湯、柴胡桂枝湯を使い分ける<br>
心不全―木防已湯<br>
急な動悸―三黄瀉心湯<br>
「五苓散」はさまざまな救急の場面で使える<br>
悪酔い、二日酔い<br>
めまい<br>
乗り物酔い<br>
飛行機が降下する時の耳の痛み<br>
子どもの嘔吐<br>
脳浮腫<br>
コラム 五苓散+小柴胡湯が効果的なその他の病気<br>
「葛根湯」は胸から上に幅広く効果を発揮<br>
【乳腺炎】<br>
【母乳のコントロール】<br>
【首のリンパ節炎】<br>
【顎関節症】<br>
【中耳炎】<br>
【眼精疲労】<br>
「抑肝散」は気持ちの高ぶりを抑える<br>
怒り<br>
認知症<br>
<br>
第4章 慢性の病気にここまで効く<br>
「炎症性の皮膚疾患」は微小循環の改善がカギ<br>
アトピー性皮膚炎―温清飲<br>
尋常性乾癬―桂枝茯苓丸加.苡仁<br>
「女性」の血のめぐりをよくする漢方薬<br>
月経困難症―加味逍遥散<br>
冷え症―当帰芍薬散<br>
不妊症―八味地黄丸<br>
「多愁訴」はポイントとなる症状で処方が変わる<br>
こんな多愁訴がみられたら「女神散」<br>
こんな多愁訴がみられたら「柴胡加竜骨牡蠣湯」<br>
こんな多愁訴がみられたら「半夏厚朴湯」<br>
こんな多愁訴がみられたら「炙甘草湯」<br>
こんな多愁訴がみられたら「柴胡桂枝乾姜湯」<br>
こんな多愁訴がみられたら「桂枝加竜骨牡蠣湯」<br>
コラム 体質別・うつ傾向に効果的な漢方薬<br>
高齢者の生命力を引き上げる漢方薬<br>
生まれ持った生命力の衰えを防ぐ―八味地黄丸<br>
睡眠パターンを改善し、精神面の安定を図る―酸棗仁湯<br>
胃腸機能を高め、免疫能を向上させる―六君子湯<br>
排尿障害―清心蓮子飲<br>
高血圧―症状に応じて使い分ける<br>
慢性前立腺炎―桂枝茯苓丸<br>
長期入院による呼吸器感染症―清肺湯<br>
夜間せん妄―甘麦大棗湯<br>
<br>
第5章 漢方薬の上手な利用法Q&A<br>
主な参考文献<br>
病院リスト
内容説明
漢方薬は身体にじっくり働きかけ、体質を改善していく薬という認識が強いが、実はその誕生時から急性期の病気を標的に開発されてきた。約2000年前、腸チフスやコレラなど急性疾患で亡くなる人が多かった時代に求められてきたので、漢方はその黎明期から救急医学であった。急性期の病気に対し、驚くほどの速効性と切れ味を発揮すること、これが漢方薬の真骨頂。最近では、多成分で構成される漢方薬の薬理学的効果が解明されつつあり、西洋薬と同じように、東洋思想を抜きに処方することが可能だ。「サイエンス漢方処方」を提唱する第一人者による斬新な漢方論!
目次
第1章 漢方薬は速効性のある科学的な薬だった(漢方薬は昔から急性期の薬だった;西洋薬の利点と落とし穴 ほか)
第2章 漢方薬の速効性を支える3つの柱(免疫力を高め、過剰な炎症を抑える;微小循環障害を改善する ほか)
第3章 急性の病気にここまで効く(日常的に起こりやすい病気;すぐ治したい不快な症状 ほか)
第4章 慢性の病気にここまで効く(「炎症性の皮膚疾患」は微小循環の改善がカギ;「女性」の血のめぐりをよくする漢方薬 ほか)
第5章 漢方薬の上手な利用法Q&A(一般の人が上手に漢方薬を利用するためのQ&A;医者が上手に漢方薬を利用するためのQ&A)
著者等紹介
井齋偉矢[イサイヒデヤ]
1950年、北海道生まれ。北海道大学卒業後、同大学第一外科に入局。専門は消化器外科、肝臓移植外科で日本外科学会認定専門医。1989年から3年間オーストラリアで肝臓移植の臨床に携わる。帰国後独学で漢方治療を本格的に始め、現在、日本東洋医学会認定専門医・指導医。2012年にサイエンス漢方処方研究会を設立し理事長を務める。医療法人静仁会静仁会静内病院(漢方内科・総合診療科)院長(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
M.O.
Sakie
hinako
kanako
Asakura Arata