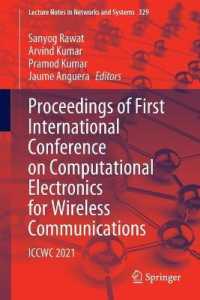内容説明
健康診断では異状なし、しかし、確実に心身の疲労を感じている―入社10年を過ぎたまさに働き盛りの人々を蝕む“勤続疲労”は、日々、会社で仕事をする私たちがさらされている脅威です。これを放置すれば、知らぬ間に心身の健康を害し、深刻な結果をもたらしかねません。疲労蓄積の原因やそれへの気づき、個人レベルでの対処法、さらには会社ぐるみでの予防体制作りの実際などを、カウンセリングの実際例を交えながら紹介します。
目次
序章 「勤続疲労」を知っていますか?
第1章 勤続疲労ケースのドキュメント
第2章 勤続疲労とは何か
第3章 過重労働とストレス
第4章 企業における対応の実際
第5章 個人の対応
第6章 勤続疲労になったらどうする?
著者等紹介
夏目誠[ナツメマコト]
愛知県生まれ。1971年、奈良県立医科大学卒業。大阪府立公衆衛生研究所部長心得、こころの健康総合センター部長を経て、大阪樟蔭女子大学心理学科、および同大学院人間科学研究科教授。精神科医、医学博士。専攻は産業精神保健、ストレス科学。産業ストレス学会副理事長、産業精神保健学会常任理事、ストレス学会理事、厚生労働省労働基準局検討会委員を務める(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Humbaba
5
全てのことを完全にこなそうと思っても、現実的には達成は不可能である。だからこそ、どれか一つに絞って残りの者はそこそこ、あるいは何もできなくても良いとする。優先順位をつけるのは難しいが、自分一人で悩まずに経験者などに尋ねる。それによりしっかりとした成果を出すことが出来る可能性は高まる。2016/05/14
シュラフ
4
入社10年以上のサラリーマンは心身ともに疲労して「勤続疲労」の状態となり「うつ」に陥る危険性があるとして、ケース紹介で「うつ」に対する個人・家族の対処法をまとめている。オーソドックスな「うつ」の書物としては、こういうまとめ方になるのは分かるが、なんだか割り切れなさが残る。 この本でも、結局は「うつ」の責任を本人に押し付けているのではないか?「うつ」に追い込んだ責任者を明確にしてペナルティを与えなければ、サラリーマン社会から「うつ」を減らすという抜本的な解決策にはなりえないと思うが・・・ 2012/05/14
けんとまん1007
2
タイトルが秀逸。まさに、同じパターンだと思う。リミッターを超えた瞬間が怖い。ただ、こういうことを知っているかどうかの違いは大きい。ただ、本人がどう感じているのかが問題で、そこは、周囲の力が大きいと思う。2010/08/04
huyukawa
0
ストレスについて、労働人口が減るなか精神的なダメージの蓄積が会社にとってもダメージにつながる。次々やめる人を新しい人で埋めるやり方で運営する会社は行き詰まる、ということを考えた。上記の考え方が広まらないうちはどうしても個人の防衛が必要になってくる。以前にも増してし、たたかに働くということがいやがおうなしに求められているように思う。2016/05/08