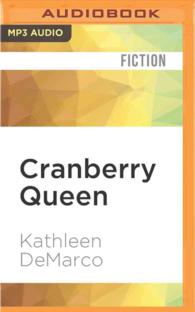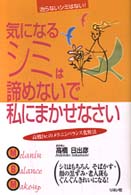内容説明
ある日突然、完全に聴力を失ったマイケルは、コンピューターで制御される人工内耳を頭に埋め込む手術を受ける。以来、彼と世界とをつなぐ感覚は機械にゆだねられ、ソフトウエアがバージョンアップされるたび、彼の聴覚も「更新」されてゆく。身体の一部を機械装置に置き換え、はからずもサイボーグとなったひとりの男の稀有な体験と、その葛藤、感慨、恋愛などを描く一人称のルポルタージュ。
目次
難聴者から失聴者へ
人工内耳手術
二つの世界の狭間で
システム起動
二三万通りの現実
脳のプログラム変更
ソフトウエアのアップグレード
人工内耳がもたらす喜びと悲しみ
サイボーグとしていかに生きるべきか
人との結びつき
テクノロジーを活かすために
マイク二・〇へのバージョンアップ
著者等紹介
コロスト,マイケル[コロスト,マイケル][Chorost,Michael]
ブラウン大学卒。テキサス大学オースチン校にて博士号を取得。現在は科学ライターとして活躍するほか、コンピューター教育のコンサルティングにも従事。サンフランシスコ在住
椿正晴[ツバキマサハル]
都立高校教諭、予備校講師を経て翻訳者となる(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
七色一味
32
読破。タイトルに惹きつけられた本。中途失聴者の、失われた聴力をマイクロチップ搭載の人工内耳を耳の後ろに埋め込んで取り戻させる──まるでSFみたいなドキュメンタリー。しきりとサイボーグという言葉を連発しているのは、それだけ抵抗があるからかな。聾唖者と中途失聴者の第一言語の違い、人工内耳を埋め込むことによる哲学的問題、そしてより技術的な問題と、多岐に渡って論じられているが、実は結構なページを割いているのが、異性との問題(笑) いやまぁ、例え本人サイボーグって言っても、その辺りはやはり生身の人間ですから……。2013/06/02
更紗蝦
14
人工内耳を頭に埋め込むことによって「サイボーグ化」した聴覚障害者の著者が、機械によって変化した生活や心理について綴ったルポルタージュです。SFの世界では大抵はサイボーグ技術といえば人間を超えるための手段として登場しますが、現実ではハンディキャップを負った人が人間らしい生活を送れるようにすることを目的としており、ヒロイズムからはおよそかけ離れています。実際にインプラントを埋め込んだ著者だからこそ、テクノロジーの可能性とその限界に関する考察は説得力があり、特にトレーニングの重要性に関する記述は興味深いです。2015/06/22
chroma
2
人工内耳埋込術を受けた著者のモノローグ。人工内耳についての話とともに私生活なども語られる。原題の「Rebuilt」には人工内耳によって聴力を取り戻しただけでなく、外界の認識も変化し自分自身を「再構築」したという意味が含まれていると思うので、邦題にはちょっと違和感を感じる。またドロップアウトした大学ではポストモダンの文化理論のゼミを取っていて、専門用語をうまく使うのが苦手だった著者が、「脱構築」や「再構築」を踏まえて、専門用語ではなく平易な文章で自分自身の体験を綴ったものと思われる。神経可塑性が興味深い。2023/11/10
北条ひかり
2
5時間29分(岩手県立視聴覚障害者情報センターと音訳者さんに感謝) 身体機能の一部を電子機器に置き換えてサイボーグになることは、先天性の障害者で医学では改善されない僕にとっては夢である。本書は、母親の風疹罹患が原因で先天性の難聴であった著者が、30代後半に完全失聴してしまったため、コンピューター制御の人工内耳インプラントを埋め込んでサイボーグになった実話に関するモノローグである。サイボーグ化された聴覚については一から学び直し、ソフトウェアがアップデートされればまた学び直しと実に大変だが、それでも羨ましい。2015/08/30
Yumikoit
2
ノンフィクション。タイトルが秀逸。 サイボーグって何?義手義足だったら?人工関節?いやいや、彼によるとコンピュータ制御された人工機能に置き換える必要があるらしく。うん。確かに納得。 難聴として生きてきた半生から、突然完全失調者になり、人工内耳を体内に埋め込んだ彼の体験談。自らもサイエンスライターとして生活する彼だからこそのウィットにとんだ文章。 外部端末との接続が、端子に埋め込まれた磁石によって介在される。ニーブンのタプスや攻殻機動隊だとちゃんと端子が出てるけど(笑)現実の方がエキサイティングだ。2014/08/10