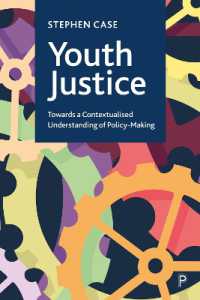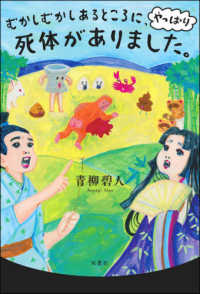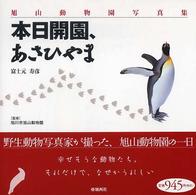内容説明
誰か一人が失敗の責任を負い、悪者退治で一件落着。時代劇ではあるまいし、こんなことを続けていたのでは、日本の組織は永久に生まれ変わることはできない。人間は失敗をするものであり、管理強化や精神論で対処しようとしても不毛だ。むしろ「失敗はなくならない」ことを前提として、しなくてもよい失敗を起こさせない仕組み作りの重要性を説く画期的失敗論。
目次
第1章 失敗に関する三つの教え
第2章 信用と隠匿は表裏一体
第3章 楽しく学べば身によくつく
第4章 効率向上の工夫が効率を蝕む
第5章 仕組み、からくり、物語
第6章 失敗したら威張って組織を危機から救おう
著者等紹介
飯野謙次[イイノケンジ]
1959年生まれ。東京大学大学院工学系研究科博士課程修了後、ゼネラル・エレクトリック(GE)原子力発電部門入社。1992年、スタンフォード大学機械工学・情報工学博士号取得。2000年、技術文書翻訳やアプリケーション開発を請け負うSYDROSE LPを設立、ゼネラル・パートナーに就任。2002年より、特定非営利活動法人「失敗学会」副会長(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ともとも
17
何事にも失敗は付き物、その失敗したあとが大事! 開き直りにも思いつつも、いつまでも失敗に対してクヨクヨとしていると さらに負のスパイラルに陥ってしまうので、失敗から失敗しない方法を学ぶ。 「失敗は成功の母」とはこういったことなのかな?としみじみ思わされてしまいました。 自分や他人の失敗に寛容になる、そして、その対処法を共に考え、 行動する、失敗を前向きに考え、次に生かす。そうすると失敗が少なくなる。 とても合理的だなと、いろいろと学び、考えさせられてしまいました。2016/10/09
Humbaba
8
どれほど頑張っても,人は必ず失敗を犯す.大切なことは,失敗を失敗のまま放置せずに,なぜそれが起きたのかを認識し,共有することである.失敗は隠しがちになるということを認め,それでもうまく回るように対処をする必要が有る.2012/01/01
aya
1
失敗したらその経験を抽象化して知識にする。 応用化して広がりを付けることで、失敗を未然に防いだり、起こっても対応しやすくなる。 2020/04/27
Humbaba
1
人間である以上は,ミスは必ず起こり得る.大切な事は,ミスをしないことではなくてミスをしたときに同フォローするかということである.どのような状況でミスを起こりやすいかを調べて,それに対処するにはどうすればよいかを考えれば,効率的なシステムが出来上がる.2010/08/03
縁
1
レポートで読みました。何度も同じフレーズを繰り返しているかんじです。入門書としてヒューマンエラーのことを頭に入れたい人向け。2010/01/10
-

- 和書
- 太陽の子 新潮文庫