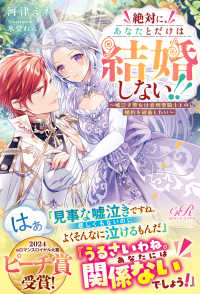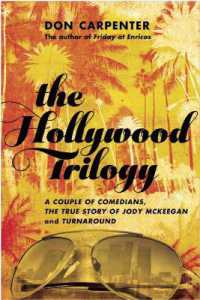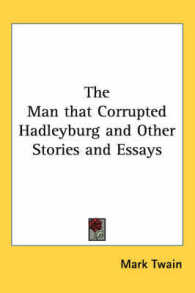感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
nagoyan
11
優。あの民法Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳの著者による。第1章は日本が西欧近代法体系を継受する、その壮大なプロジェクトの意義を、穗積珍重以前、穂積兄弟の事跡を振り返りながら、解き明かしていく。第2章では、民法を例にとり、今、法律を学ぶということの意義を明らかにする。試験制度に関心が集中した司法制度改革は、むしろ、日本社会に高いリーガルリテラシーを齎していた拡散型の利点を損なう結果となったとする著者の指摘は鋭い。2023/05/31
Yuichi Tomita
3
内田貴氏が、高校生に対して法学とは何かについて述べた講義を収録したもの。ただし、開成と筑駒の学生向け……。 法律は言語と似ており、法律の考え方を理解するリーガルリテラシーということばで自己の主張を説明している。昔は弁護士資格がなくてもリーガルリテラシー高い公務員、会社員がいたが、弁護士に集中していないか。 司法制度改革は失敗と言いきっているのも印象的。2023/01/02
左手爆弾
2
「法学」とは、特殊な学問である。各国ごとに法律の内容だけでなく、考え方も違う。そうした点を、筆者は一貫して言語との類比で語る。単なる規則の集積ではなく、文化や伝統を学んでこそ、法学となる。近代市民社会を作る上で必要不可欠な契約や債務といった概念を翻訳し、現実の複雑さを法学の空間の中で扱うことができるようにする。これこそが明治以降の法学の責務であった。言われてみれば、民放や憲法ではなく「法学」という学問の入門書は少ないので、本書は貴重なのかもしれない。2023/01/20
Praesumptio cedit veritati
2
債権法改正に関与した民法学研究者による、高校生への講義をまとめた本。自らが法学を学んだ過程に触れつつ法学の特徴を説明した上で、同じ著者による『法学の誕生』(筑摩書房)で描かれた明治期の法学の形成史を、穂積陳重・八束を中心に素描する。そこでは、法学の概念の普遍性の高さ、そして「我々は何者か」を西洋法学の概念を用いて説明するという使命感の強さが描かれる。民法の教科書を執筆した際の問題意識や、近時の日本の法実務と法学の関係をめぐる問題意識が示され、高校生との質疑が収録されている(高校生の質問が高度)。2022/08/15
aochama
1
民法の大家である内田先生の高校生向けの講演を書籍にしたもの。前半は日本に法学が定着するまでの歴史がとても分かりやすく、非常に得心しました。後半は、内田先生の教科書が誕生する動機の他、そもそも民法とはなんぞという話、法的リテラシーの重要性と現在とこれからの姿にも言及。いずれの話題も興味深く有用な本でした。それにしてもこんな講演を聞ける機会がある超一流校の高校生は、幸せですねー2022/11/28