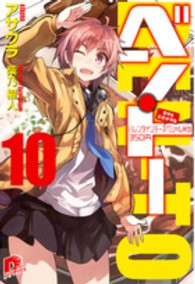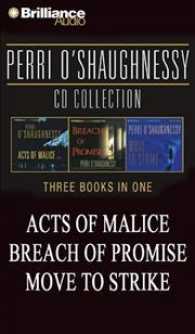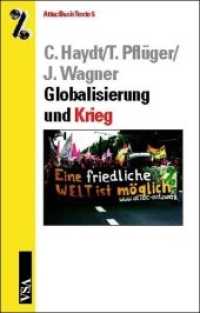目次
序 国際日本文化研究センターにおける怪異・妖怪研究
1 妖怪文化研究の現在
2 妖怪データベースからの創造―公開一五周年を迎えて
3 怪異・妖怪研究の新時代―日文研共同研究を礎に
4 もののけシンポジウム「怪異・妖怪研究と日文研」
5 文化コードとしての「妖怪」
6 日文研大衆文化研究プロジェクト(近世班)活動記録
著者等紹介
小松和彦[コマツカズヒコ]
国際日本文化研究センター名誉教授。専門は文化人類学・民俗学
安井眞奈美[ヤスイマナミ]
国際日本文化研究センター教授。専門は文化人類学・民俗学
南郷晃子[ナンゴウコウコ]
国際日本文化研究センター技術補佐員。専門は説話、伝承(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
テツ
16
幼い頃の夏休みに祖母に買ってもらった水木しげるの妖怪図鑑を初めて目にしてから今に至るまで『妖怪』という二文字を目にするだけでときめいてしまう(病気) 夜も闇も薄くなり人の心の動きも解明されつつある現代社会に生きるぼくたちは暗がりや本能的な恐怖の中に怪異を齎す何かを見出す能力を失ってしまったけれど、情報として、怪異譚として記録に留められている限りは彼らが死に絶えることはない。根源的な恐怖や不安に理由づけをしようとする文化的な発明である妖怪。無知蒙昧から生まれたくだらない迷信とは最もかけ離れた存在。2023/11/27
mittsko
6
「最前線」「伝統と創造」「進化する」と続いてきた「妖怪文化叢書」全四巻の四冊目。2022年刊。論文集ではなく、共同研究におけるレクチャー、シンポ、ディスカッションなどの記録を含む。日文研の大衆文化研究プロジェクトの近世班のお仕事で、北京やパリ、イタリア、韓国など、海外での研究発信と成果を集めているところが、いかにも「新時代」ですね。「妖怪データベース」の構築運用、利用について多くの紙幅が割かれるところなども。2023/08/21