内容説明
フランス近代小説の歴史を根本から変えた『ボヴァリー夫人』の新訳(新潮文庫)を手がけた著者が、貴重な翻訳体験で遭遇した数多くの疑問を糧に、過激なテクスト論者の視線で、文学における「表象革命」を成し遂げたフローベールの言葉の秘密に迫る。
目次
第1部 自由間接話法(「そして」に遭遇する;「自由間接話法」体験;表象革命としての「自由間接話法」;「農業共進会」―対話をはじめる二つの言説)
第2部 テクスト契約(ほこりと脈拍―テクスト的共起をめぐって;主題論批評と「テクスト的な現実」;隣接性と類縁性;テクスト契約をめぐって;“書くこと”の極小と極大;ほこり立つテクスト)
著者等紹介
芳川泰久[ヨシカワヤスヒサ]
1951年、埼玉県生まれ。早稲田大学大学院後期博士課程修了。早稲田大学文学学術院教授(フランス文学、文芸評論)。専門は、バルザック、ヌーヴェル・クリティック、テクスト論(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
三柴ゆよし
19
『ボヴァリー夫人』を翻訳した著者による、古典精読の新しい試み。翻訳に際し、フロベールの特殊な文体とそこに頻出する語彙(接続詞「そして」と自由間接話法、テクストに偏在する「ほこり」と登場人物のこめかみで脈打つ「音」)をどのような日本語に置き換えるかを追求すれば、当然のごとく、フロベールはなにゆえ斯様な表現に取り憑かれたのかを熟考することになる。その思考の過程がとにかくおもしろく、ぐいぐい読ませるが、単なる翻訳奮闘記、あるいは作家論作品論を超えて、小説表現そのものの可能性にまで肉薄した名著ではないかと思う。2020/04/30
ヤマニシ
1
「描かれるべき内容に、描こうとしている形式じたいを一致させようとするクラチュロス的な<書き方>を、フローベールは選択している。」(p190)2021/09/29
Skel_san
1
「rigoureux(厳格)なテクスト論者」が一字一句を緻密に読み込んでいく良書である。テクスト外の想像力に依拠するテマティスムの問題点を指摘する箇所はかなり勉強になるし、その延長で蓮實重彦『「ボヴァリー夫人」論』への言及もある。欲を言えば、自由間接話法についての説明がもう少し欲しい。フロベールはなぜ神の視点を採用しないかということや、語り手と視点の問題をもう少し厳密に──「内的焦点化」、「外的焦点化」といったジュネットの用語を使用して──説いて欲しかった。2016/12/21
ゴリラ爺
0
再読。『ボヴァリー夫人』を新訳した著者による「我、発見せり!」が書かれた10章だが、ここで論じられていることは既に自家薬籠中の物だったらしく、全てその前提で読んできたものだから、新しい発見はなかった。もう読み返す必要のない本として記憶に留めておこう。2024/11/09
N
0
すげー2020/07/13
-
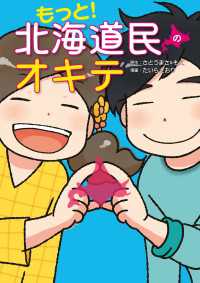
- 電子書籍
- もっと! 北海道民のオキテ 中経☆コミ…


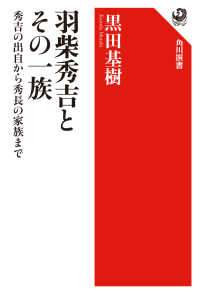
![MINECRAFT かたづけ名人になれるインテリアトートBOOK TNTver. [バラエティ]](../images/goods/ar2/web/imgdata2/42990/4299044312.jpg)




