内容説明
本書は、人生や過去の出来事の経験をインタビューすることによって人びとのアイデンティティや生活世界、さらにローカルな文化や社会を理解するための社会調査の手引き書である。
目次
第1章 ライフストーリー・インタビューをはじめる(調査研究のテーマは、どのように決まるか;調査をはじめるにあたっての倫理的な問題;語り手の選択とリアリティのとらえ方;ライフストーリーの構成;評価基準の再考)
第2章 ライフストーリー・インタビューをおこなう(インタビュー・エンカウンター―語り手との出会い;インタビューをおこなう;コミュニケーションとしてのインタビュー;語り手にとってのインタビュー)
第3章 インタビュー・テクストを解釈する(ライフストーリーの整理;個人的記録資料;鍵になる言葉と分析的カテゴリー;社会的コンテクスト;ストーリーのダイナミズム)
第4章 ライフストーリーを書く/もちいる(ライフストーリーを語るということ;作品化の手法;語りのないライフストーリー論文;エスノグラフィーとしてのライフストーリー;作品化と倫理の問題)
著者等紹介
桜井厚[サクライアツシ]
現職、千葉大学文学部教授。専攻、ライフヒストリー/ライフストーリー研究、社会問題の社会学
小林多寿子[コバヤシタズコ]
現職、日本女子大学人間社会学部教授。専攻、現代社会学(ライフヒストリー論、都市社会論)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
アナクマ
34
聞き書き手法のいちスタイルを、準備・実行・解釈・書く、の4章に分けて指南する。◉2章_実行「テープが止まってから最も重要なことが語られるかもしれない」「ストーリーを語ることが人生の再吟味である(物語効果。語り手に生じるカタルシス)」など、聞き書きの持つ核心がそこここに織り込まれています。2005年刊。◉ここ10年ほど、あらゆる媒体において素人ドキュメントの隆盛を感じます(それは社会科学の成果だと思う)。例えば、何気ないつぶやきが誰かに拾われて輝き出すとか、人生の悲喜劇が名刺のように精錬される、とか。 2021/11/06
アナクマ
24
2章_p.94〜再読。曰く、インタビューは相互行為。◉「聞き手は語り手にとって特別な存在になっている可能性がある」(小林)「緊張と困惑に満ちたコミュニケーションの場。他者を発見していく豊かさを持つ場」「〈いま-ここ〉の多様性が、現実を構築し意味を産出していく契機」(加藤裕治)と、わずか4ページに。◉言い換えればこれは『かかわり方のまなび方』(西村佳哲著)。つまり聞き書きは、コミュニケーション・トレーニングでもある。さらに自分なりに意訳すれば、肝心なことは『君あり故に我あり』(サティシュ・クマール著)。→2021/11/13
いとう
8
p48 社会調査が・・人々の主観的意味を求めることを目的とする限り・・語り手の視点は欠くことができない。その意味でライフストーリー研究法は、調査テーマの当該主体にとってはきわめて妥当性の高い方法であるといえるだろう。 p144語り手が個人経験の語りではなく、説明や評価に終始してしまうと・・個人的経験を解釈することができなくなってしまうので注意が必要 p163なぜ人は語るのか?・・その後の人生を決めたまさに決定的な経験があるから(エピファニー経験)←これをインタビューで聴取することが重要2023/07/19
たかこ
6
ことばはフシギである。ことばにする前に「経験」があるのではなく、ことばにしたとたんに「経験」が結晶のようにその場でキラキラ生まれてくる。そして、その「経験」を舌の先で転がしながら身体になじませて腑におちるまで語り直しているうちに、しっかり自分の「経験」となって定着して、やがては自分の未来の「経験」をつくっていくように方向づけさえするのである。自分の人生を語ることは自己肯定感をもらたることであろう。そしてインタビューが進むうちに、ライフストーリーインタビューがもつ「人生の再吟味」の側面に魅了される。2019/02/15
ながしま
1
仕事の参考に読んだが面白かった。セカンドキャリアでこういう仕事ができたらいいなと思った。2020/02/02
-

- 電子書籍
- 不思議の国の白ウサギ【タテスク】第16…
-
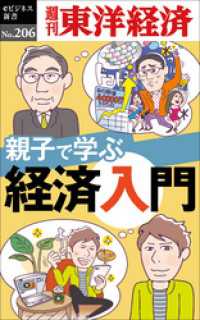
- 電子書籍
- 親子で学ぶ経済入門―週刊東洋経済eビジ…







