内容説明
「人類最古の書きことば」から「21世紀末の日本語」まで、コトバと火を使用する、すべてのヒトへ贈る〈サイエンス・ノンフィクション〉第7弾。人類はコトバなしには一瞬たりとも社会生活を営み得ない。しかし、コトバについて我々はどれだけのことを知っているのだろうか?
目次
第1章 知られざる学問、それは言語学(言語学のルーツ;言語学の科学性;経験科学としての言語学;実証科学をめざす言語学;言語学の魅力)
第2章 言語とは何かを考える(コミュニケーションの手段;二重の分節;恣意的記号の体系;体系と構造;無限の生産性)
第3章 言語学をマスターする(学問的位置づけ;音声学;音韻論;文法論;意味論)
第4章 暮らしの中の言語学(より身近な言語学のために;ヤハリ、ヤッパリ、ヤッパシ、ヤッパ;「コートジボワール」とは何事だ;「嫌音権」の確立をめざして;ヘタなホンヤク、社会のメイワク;21世紀末の日本語はどうなるのか?)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
niko
0
言語学が、観察と実験によって得られた客観的なデータを操作することによって解明される経験科学であるという部分を否定しているわけではないのですが、仮説中心のツッ走りだという感はありました。ただそれは私がまだまだ勉強不足だからだと思っていましたが、それだけではなかったのかもしれませんね。また、私の中で「科学=自然科学」のイメージがあることも否定しません。ただ、実際に「言語学は自然科学」というような意見も何度も聞いた事があるので、上で書かれている「自然科学」と同等に扱えるものなのか?とは思っていました。2009/07/04
ととろ
0
大学の社会言語学の教科書。言語学は日本では人文科学と同様の扱いを受けているが、この学問は自然科学や社会科学とも深く関わりがあります。講義で扱ったのは第4章「暮らしの中の言語学」です。やはり→やっぱり→やっぱし→やっぱの変化を分析した回が印象に残っています。2010/07/25
-
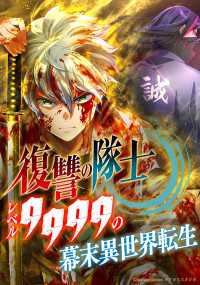
- 電子書籍
- 復讐の隊士 - レベル9999の幕末異…
-
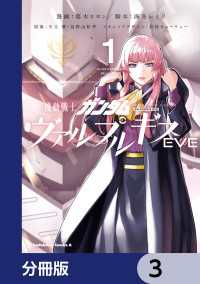
- 電子書籍
- 機動戦士ガンダム ヴァルプルギスEVE…
-
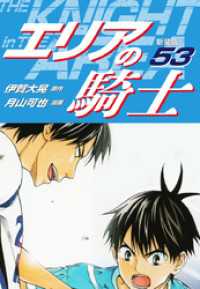
- 電子書籍
- エリアの騎士(新装版) 53
-
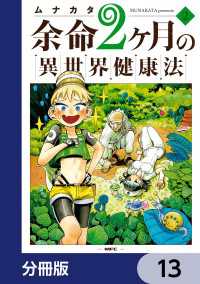
- 電子書籍
- 余命2ヶ月の異世界健康法【分冊版】 1…
-
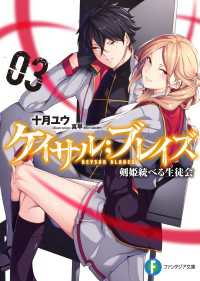
- 電子書籍
- ケイサル;ブレイズ3 剣姫統べる生徒会…




