内容説明
ちょうど、現代と同じく時代の転換期であった明治時代にも、「妖怪」についての見方を示した二人の人物がいた。一人は、「哲学」の普及をめざして東洋大学を創立した井上円了である。明治20年代から『妖怪学講義』などを出版し、近代人の特質である合理的な見方に立って、日本人の「妖怪」に関するものの見方・考え方を、新しい時代のなかで問い直したのであった。それからしばらくのちに、もう一人の人物である柳田国男が、民俗学を提唱するなかで、妖怪を「神と人」との関係から捉え直したのであった。現在の妖怪に関する見方は、この二人に代表される流れを引き継いでいるが、新時代への転換を迫られている現代において、ふたたび現れた人々の「妖怪」への関心がなにに起因するのか、本書は、それを考えるためにも、改めて「妖怪と日本人のかかわり」の原風景を、多くの人々とともに振り返った。
目次
妖怪とうそ話―遊び心と想像力
妖怪たちの諸相―資料から見る
コレクターの心にひそむ妖怪
妖怪と仏教―怪しき「異形のものたち」
民俗学からみた妖怪
井上円了の妖怪学―その今日的な意義
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
烟々羅
14
通読できずに図書館に返すが、次回は再読の気持ちになるだろうからの登録その2。 東洋大学は井上円了が作った大学で、円了ってひとは(おそらく)化野燐「蠱猫」シリーズでモデルにされている人物なのだけど、実際に妖怪(についての伝承)をあつめ、分類するときの姿勢はこうだったらしい ……という辺りが今回の注目点でした2012/05/01
わ!
4
2000年に出版された本なのですが、つい最近見つけることが出来て、つい最近に買いました。一応、妖怪学(まだ怪異学が出来る前かも…)の入門書という体をとっているのですが、どちらかというと妖怪マニア向けです。本当に妖怪学に入門したい場合は、小松和彦さんや、京極夏彦さんの妖怪学の本を読んだ方が妖怪学は、理解しやすいです。この本は、妖怪学のイベントでの講演を本にしたもので、妖怪の専門家以外人が多く選出されて講義をしています。どちらかというと各専門家が自分の分野と妖怪学との接点を述べている様な論文集となっています。2024/11/12
けーすけ
3
民俗学の一つである妖怪学は井上円了に端を発する。妖怪と神との区別は難しく、共通する点も相反する点も混在する。妖怪の発生には当然人間の迷信がある。このような迷信は消えることがない。つまり人間の想像によって不思議な存在と信じられるものであるのだ。妖怪学は他の学問から邪険にされたそうで、東洋大学内でも学閥は小さいそうです。2014/11/17
白義
2
つまらなくはないけど、妖怪入門というより、妖怪に関するシンポジウムをまとめた本。そこそこ濃いメンバーが集まっているけど、内容がそれに比例していない感じもある。妖怪そのものに迫るというより周囲でぐるぐるだべってるような。なだいなだに期待したが専門外なのもあってこの中では一番どうでもいい文章になってるのがやや残念。しかし北原照久の講演は圧倒的に面白い。マニア心と妖怪への心構えが両立していて読んでてほっこりする文章だ2012/03/26
ぽねごん
1
それぞれ異なる専門分野の方たちの妖怪に対する考察。2013/09/28
-
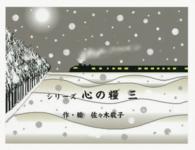
- 和書
- シリーズ心の糧 〈3〉







