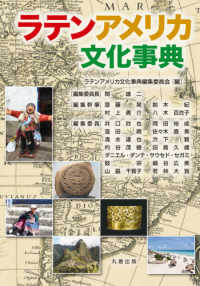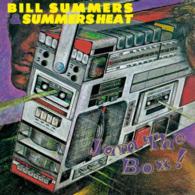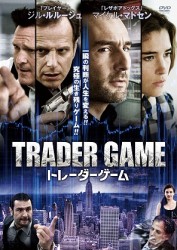内容説明
安楽死を願った二人の若き患者と過ごし、そして別れたある夏に何が起こったか―。オランダ、ベルギーを筆頭に世界中で議論が巻き上がっている「安楽死制度」。その実態とは。緩和ケア医が全身で患者と向き合い、懸命に言葉を交し合った「生命」の記録。
著者等紹介
西智弘[ニシトモヒロ]
川崎市立井田病院かわさき総合ケアセンター、腫瘍内科/緩和ケア内科医長。一般社団法人プラスケア代表理事。2005年北海道大学卒。室蘭日鋼記念病院で家庭医療を中心に初期研修後、2007年から川崎市立井田病院で総合内科/緩和ケアを研修。その後2009年から栃木県立がんセンターにて腫瘍内科を研修。2012年から現職。現在は抗がん剤治療を中心に、緩和ケアチームや在宅診療にも関わる。また一方で、一般社団法人プラスケアを2017年に立ち上げ代表理事に就任。「暮らしの保健室」「社会的処方研究所」の運営を中心に、地域での活動に取り組む。日本臨床腫瘍学会がん薬物療法専門医(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
モルク
91
合法のスイスの安楽死を求めたが叶わず緩和ケア病棟でトイレに行けなくなった時に「持続的な深い鎮静」をしてほしいという30代のすい臓癌の女性と看護師を目指していた20代の末期大腸癌の男性。この二人を通して緩和ケア医西野氏が安楽死と緩和ケアを探る。自分があるいは家族がもう確実に先がなく「耐えがたい苦痛」に苦しんでいたら、と考えると安楽死という選択肢があってもいいのかなとは思うが苦痛の度合いは個人差がありその線引きは難しい。ハードルは高くまだまだ議論を要する。私はできる限り痛みがなく安らかな最期を迎えたい。2024/11/12
nyaoko
84
もし、治る見込みのない病に侵され、耐え難い苦痛しか残されていないと知ったなら、お互いに安楽死を望みたいと夫と話した事がある。けれども、日本にはまだ安楽死の制度がない。その代わりに緩和ケアがある。苦痛を取り除き、穏やかに死ねるのならばそれはありだなあと思ってたけど…非常に難しい様だ。出来る限りの治療を施され、その痛みや苦しみはまだ我慢できると医療者から判断され、身内からは生きろ生きろと励まされ、それはまさに生き地獄。苦しみの中で死ぬよりも、安らかな眠りの中で優しい夢を見ながら死にたい。2020/09/23
夜長月🌙
72
薬では抑えられない絶望的な苦痛(肉体的もしくは精神的)がある時にあなたは安楽死を望みますか。あるいはホスピスに入りますか。それとも生きることに全力で臨みますか。著者は緩和ケアを行なっている医師であり、安楽死がたとえ日本で認められたとしても限りなく0であることを望んでいます。豊富な具体例とともに話が深められていきました。耐えがたい苦痛の定義とは何か。そしてそれを判断するのが医師でよいのか。考えさせられます。2023/09/09
honyomuhito
67
最近SNSを見ていると、時々末期の癌患者本人の書き込みを見ることがある。以前は患者本人の意思に直接触れることは少なかった。癌になったら余命を宣告されたら人生が終わってしまうのではというイメージを覆し、真摯に、大切に、そしてマイペースに生きることと向き合う人が多いように思う。著者もまたSNSを通じて、今まで気軽に話題に出ることは少なかった安楽死というものに問題提起している。医師である著者は重篤な病を被った患者の肉体的、精神的な負荷を軽減し生活の質(QOL)を改善することを目的とした緩和ケアを専門としている。2020/09/22
あつこんぐ
40
さっき痛み止めを飲んだばかりの患者さんがまだ痛みを訴えた時「さっき薬飲んだばかりやろ。もう少し我慢して」と言ってしまうことがよくあります。でも、自分が患者になった時「そんなことはどうでもいいからとにかく痛みを止めて」と思う自分がいます。本人の痛みは本人にしかわからない。患者さん自身が思うように過ごせる世の中になってほしいです。2020/12/13