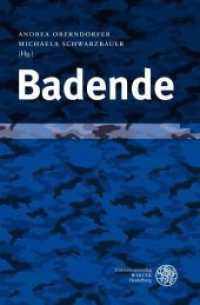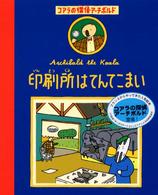内容説明
PISA(OECDの学習到達度調査)、WVS(世界価値観調査)などの国際データから、総務省・文科省の調査まで、国内外の統計データを解析すると、日本の教育の病理が見えてくる。見たくない現実も、データで示せば一目瞭然。子ども・家庭・学校・若者・社会…5つの分野の統計データから浮かび上がる、日本の教育の不都合な真実。教育問題の解決・改善は、まずこのデータを直視することから。すべての教育関係者必携のリファレンスブック。
目次
1 子ども(学力;逸脱)
2 家庭(家庭環境;保育;受験)
3 学校(教育機会;教育課程;進路;教員)
4 若者(就労;結婚;意識)
5 社会(学歴社会;格差社会)
著者等紹介
舞田敏彦[マイタトシヒコ]
1976年生まれ。教育社会学者。東京学芸大学大学院博士課程修了。博士(教育学)。専攻は教育社会学、社会病理学、社会統計学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
きいち
36
貴重な取り組み。素人の印象論が影響しがちな教育という世界だけに。◇学力と階層、地域ごとの期待水準と実際の学力との差、勉強の得意度と自尊心、理科の授業の内容と理系志向の強さ、保育士の待遇と離職率、…。時系列で、あるいは国際的に比較し、図で示すことで、当然に見えることの背景を考え、印象論の誤りを正す。◇美術やスポーツ、教養に関する経験と階層とのリンクの大きさに唖然。修学旅行や校外学習は価値高いな…。◇著者でも「教育の外部利益の計測は容易ではない」と考えるのか…。◇社会人学習に関するネタが選ばれてないのは残念。2018/07/16
シン
17
著者ブログ「データえっせい」からの抜粋本。 1年程前からブログをちょこちょこ読んでいたので、 当たり前だが目新しいことはあまりなく。 ブログの方は目から鱗のデータがあったり、 仕事に使えるデータがあったりで助かっている。 教育は国の根幹。 そこを考える上でここの知識は役に立つと思うので、 色んな人に読んでほしい1冊である。 2017/08/22
Mc6ρ助
11
日頃抱いている日本社会への違和感を教育面が中心とはいえ統計で説明してくれる。『なぜ日本の夫は家事をしないかについては諸説がありますが、私は、男女の家事スキル格差という点に関心を持ちます。夫に分担の意思があっても、スキルが低く戦力にならず、妻が一手に担うことになる。これは、学校における家庭科教育にかかわる問題でもあります。(p119)』とはいえ、これから日本をどうしていくかはデータが政治的な判断を下してくれるはずもなく、読者一人一人が出来ることを考えていくしかない。2020/03/29
ポレ
10
公表データを統計分析して社会問題をあぶり出す趣旨。ブログから抜粋した記事を加筆再構成した内容で、ひとつひとつのトピックが短く薄味な印象を受ける。着眼点や考察も独自性に欠け、全編にわたり既視感が蔓延している。もっともそのことは前書きで触れられており、常識をデータにより立証する視座は首肯できる。国際比較では日本人の特異性が顕在化していて、お上の意向に粛々と従い、なおかつ肯定的に捉えている日本人像を浮かび上がらせている。が、そこでトピックは終わってしまう。ポテンシャルを感じるだけにもったいない。2019/06/18
MASA
6
非常に面白く興味深い内容だった。やっぱりデータで示されると説得力があり、日本の現状というのをまざまざと見せつけられた感じがした。こういうデータをもっと政府の人たちが作成し国民にも知らせるべきだし、こういうデータをもとに手厚い支援をしていくことが本来の税金のあるべき使い方だと思った。内容としてはなかなかの量だが読む価値はあると思う。2020/10/22
-
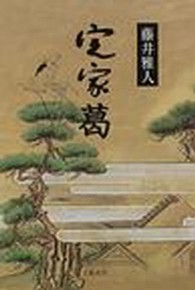
- 和書
- 定家葛