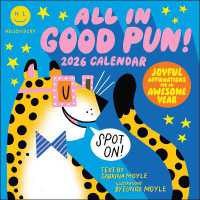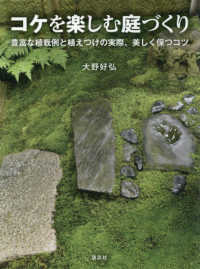出版社内容情報
データが氾濫する時代には、データではなく「森」を見よ!メディアの最前線で活動する著者の、新しい情報社会の見取り図!
インターネットは社会を便利で快適なものに変えたが、一方で人間の生命力を弱めていないか。「木を見て森を見ず」の言葉どおり、わたしたちは細部にこだわるあまり、全体を見通す目を失ってはいないか。ネットがあたりまえのものになり、データが氾濫する時代には、データではなく「森」を見よ! 数々の企業、商品開発、広告戦略、メディア、教育行政の現場に携わってきた著者が描く、あたらしい情報社会の見取り図。
■序章 森を見る力
森を見る力 1
森を見る力 2
■第一章 戦後社会の中で変質したものは何か
社会の変質
生きる力を失っていく子どもたち
戦後社会のコミュニティを壊したものは何か
就活地獄は、どこから来たのか
団塊世代論
組織の変質
「豊かさ」を目指す第一世代組織論
組織の内部崩壊
「強さ」を目指す第二世代組織
第三世代組織の暴走
戦後民主主義というコミュニティ
第四世代組織の展望
企業の変質
誰がマーケッターを殺したか
どうした、家電メーカー!
恐竜化するイオン
セブンプレミアムは「おいしい」のか
政治の変質
投票に行かなくなった若者たち
官僚という職業
政治家という職業
ギリシャと日本
■第二章 不安定な時代のアイデンティティ
コンドームが何をしたか
ニートという生き方
モンスターの時代
モンスター消費者
■第三章 メディアの現在
出版の現在
変わりつつある書店の役割と、スタバ本の革命性
ブックオフ論
電子書籍進化異論
本はなぜ滅びるのか
地方書店「好文の木」の実験
テレビの現在
広告とは何か
テレビを見るべきか、インターネットを見るべきか、それが問題である
音楽・ゲームの現在
パチンコとソーシャルゲーム
売れないCD。でも音楽の時代は進む
僕らが「ジョブズの魂」から学ぶもの
■第四章 インターネットが何をしたか
生命・情報・社会
Twitter私論
アフター・インターネットの世界
池上彰は「まとめサイト」だ
■第五章 3・11以後の社会
原発を止める、ただひとつの道
地域で生きるということ
インターネット時代の新しい生き方
オーナー・シェフ型アーティストの登場
こども芸術大学
競争の終わり
支援活動はしません
未来フェスの可能性
魂のオリンピック
あとがき 追悼・林雄二郎さん
【著者紹介】
デジタルメディア研究所・所長。1972年、音楽雑誌「ロッキング・オン」を創刊。1978年、全面投稿雑誌「ポンプ」を創刊。その後、さまざまなメディアを開発する。現在、未来フェス代表、未来学会理事、阿佐ヶ谷アニメストリート商店街会長などを務める。『企画書』(宝島社)、『メディアが何をしたか?』(ロッキング・オン)、『ナゾのヘソ島』(アリス館)、『一応族の反乱』『生意気の構造』(共に日本経済新聞社)、『シフトマーケティング』(ビジネス社)、『21世紀企画書』(晶文社)、『インターネットは儲からない!』(日経BP社)、『暇つぶしの時代』(平凡社)、『やきそばパンの逆襲』(河出書房新社)、『風のアジテーション』(角川書店)、『自分探偵社』(オンブック)、『ドラマで泣いて、人生充実するのか、おまえ。』『希望の仕事術 』(共にバジリコ)ほか共著、編著多数。
内容説明
インターネットは社会を便利で快適なものに変えたが、一方で人間の生命力を弱めていないか。「木を見て森を見ず」の言葉どおり、わしたちは細部にこだわるあまり、全体を見通す目を失ってはいないか。ネットがあたりまえのものになり、データが氾濫する時代には、データではなく「森」を見よ!数々の企業、商品開発、広告戦略、メディア、教育行政の現場に携わってきた著者が描く、あたらしい情報社会の見取り図。
目次
序章 森を見る力
第1章 戦後社会の中で変質したものは何か
第2章 不安定な時代のアイデンティティ
第3章 メディアの現在
第4章 インターネットが何をしたか
第5章 3・11以後の社会
著者等紹介
橘川幸夫[キツカワユキオ]
デジタルメディア研究所・所長。1972年、音楽雑誌「ロッキング・オン」を創刊。1978年、全面投稿雑誌「ポンプ」を創刊。その後、さまざまなメディアを開発する。現在、未来フェス代表、未来学会理事、阿佐ヶ谷アニメストリート商店街会長などを務める(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
yamaneko*
ceskepivo
nizimasu
芸術家くーまん843
檜村
-

- 洋書
- Obras