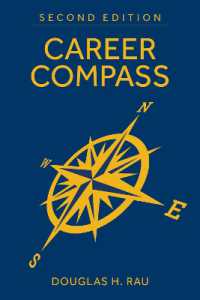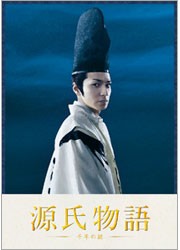出版社内容情報
ナチスドイツのユダヤ人大虐殺=ホロコーストで大きな役割を果たし、1960年、逃亡先のアルゼンチンでイスラエルの秘密警察によって逮捕され、絞首刑になったアドルフ・アイヒマン。本書は、アイヒマンの息子にあてた公開書簡の形式をとっている。世界がグローバル化し、誰もが組織の歯車になりかねない時代に、個人の責任とはなにか、上意下達の組織、社会でいかにしてアイヒマン的存在から抜け出すか。自分で考える力の必要性を問う哲学の本。
内容説明
ナチスドイツのユダヤ人大虐殺の責任者と目されたアドルフ・アイヒマン。本書は、その息子クラウスにあてた哲学者の公開書簡である。今日、世界中が最大の成果と効率をめざし、人々は経済活動に駆り立てられている。世界がひとつの「機械」になるとき、人間は機械の「部品」となり、良心の欠如は宿命だろう。かつてアイヒマンは、「自分は職務を忠実に果たしただけだ」と言った。はたしてわれわれにアイヒマン的世界から脱け出すチャンスはあるのだろうか?だれもが「アイヒマン」になりうる不透明な時代に輝きを放つ、生涯をかけた思索。
目次
クラウス・アイヒマンへの公開書簡(二度の喪失;もっと多くの喪失;尊敬がないところには哀悼も生まれない;人を尊敬する者のみが尊敬を受けることができる;怪物的なもの;暗い世界;地獄のような法則 ほか)
クラウス・アイヒマンへの第二の書簡(無関心に反対する)
著者等紹介
アンダース,ギュンター[アンダース,ギュンター][Anders,G¨unther]
1902年、ブレスラウ(現・ポーランドのブロツワフ)で生まれる。「他者」を暗示するアンダースはペンネームで、本名はシュテルン。両親はともに著名な児童心理学者であった。フライブルク大学、マールブルク大学でフッサールとハイデガーに哲学を学ぶ。29年、ハンナ・アーレントと最初の結婚。33年のナチの政権獲得後にパリ、つづいて合衆国に亡命。ジャーナリスト、工場労働者として働く。50年、ヨーロッパに戻る。戦後は国際的反核運動の指導者となり、58年には来日した。オーストリア文化賞、ウィーン出版文化賞、アドルノ賞などを受賞。92年、ウィーンで死去
岩淵達治[イワブチタツジ]
1927年、東京生まれ。東京大学文学部独文科卒。学習院大学名誉教授、ミュンヘン大学名誉博士。ドイツ文学、演出家。湯浅芳子賞、日本翻訳文化賞、ドイツ連邦政府レッシング翻訳家賞受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
みねたか@
ぼけみあん@ARIA6人娘さんが好き
バルバロ
とくま
とんこつ