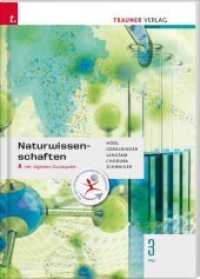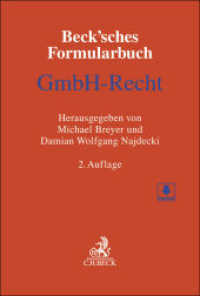感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
どんぐり
38
「写真はすべて死を連想させる(メメント・モリ)ものである。写真を撮ることは他人の(あるいは物の)死の運命、はかなさや無常に参入するということである。まさにこの瞬間を薄切りにして凍らせることによって、すべての写真は時間の容赦ない溶解を証言しているのである」。見えるものを記憶にとどめる「写真」をめぐるソンタグの思索。写真のもつ美や醜、文学や絵画との比較、映像世界にまで話は及ぶ。ソンタグの文章は決して読みやすいとはいえないが、写真のもつ意味を社会・文化的視点から論じていて刺激的だ。 2012/12/16
zirou1984
37
「飛行機事故やテロリストの爆弾破裂等の激しい事件に巻き込まれた際の経験を「映画みたいだった」と人々が主張するのは今では普通になっている」―これは911に関する話ではない。スーザン・ソンタグが70年代に執筆した本作で述べた言葉である。写真とは瞬間を永遠に留める芸術であるが、瞬間の当事者を拒否するものでもある。「写真は同情を生み出しもするが、同時に同情を切りつめ、情緒を引き離したりもする。」ソンタグの抵抗の言葉は切りつめ捨てられた感覚を懸命に拾い上げようとする、世界が安易なリアリズムに塗り潰されてしまう前に。2013/08/05
井月 奎(いづき けい)
35
極めて優れた論評、思考です。写真のありようや絵画との関係性、アーティストのコメントや作品から、写真の可能性と限界をあぶりだしています。引用や作品紹介が豊富であり、汲めども尽きぬような読書になるのは、嬉しい悲鳴をぐっとこらえる努力を強いります。そしてこれは良い悪いではないのですが、著者は斜めにものを見ます。それは新鮮な視線と視点をもたらせますが、力強く奥深くへと届かせるには限界があります。それを理解したうえで利用すればよく、芸術論は芸術指南でもありますから、読んだ後にどう活かすのかが肝要だとおもうのです。2016/06/08
chanvesa
16
「写真を撮るということは、写真に撮られるものを自分のものにするということ(10頁)」と、「あらゆるものを撮影する必要があることの究極の理由は、まさに消費そのものの論理にあるといえる(181頁)」の論理の飛躍はなんであったのか、宿命的な推移だったのか。携帯電話やスマートフォンにカメラが付いて、とっておきの時の記録だった行為は、日常的な消費的な記録になっていったのは確かだ。しかし「現実の事物に対するのとちがって写真映像になった不安な事件にはひとは傷つきやすい」という3.11でも真理となった命題の証明はない。2014/10/06
Ecriture
16
1977年の時点ではそれまでの写真論のうちでベストと称された写真論の古典。もとは随筆だったとソンタグが言うように、論文調で的を絞って書かれた文章ではないが、その分多岐にわたるテーマを軽やかに論じている。過ぎ去る時間をなんとかとどめようという写真。観光地を植民地化する写真。残酷さを飼い慣らすための写真。アメリカと中国における写真の違い。次から次へと話題は移っていくが、どれも軽すぎることはない。特にパスポートとしての写真という論点はあまり見たことがなかったので参考になった。これは読んどくでしょう。2011/06/04
-

- 和書
- おもしろ看護血液学