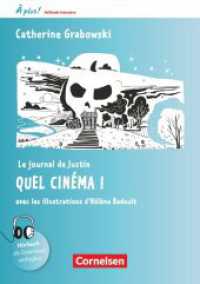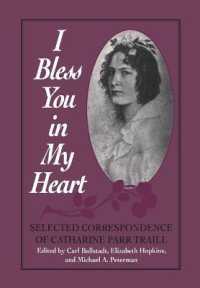出版社内容情報
カップル、家族、コミュニティからグローバル化経済の領域まで、人間社会の循環的関係を鮮やかに析出!贈与交換論の最先端議論!
結婚式に呼ばれれば祝儀をもっていくし葬式の参列には香典を持参する。そして祝儀や香典には半返しや七分返しでお返しがくる。さまざまな機会に贈り物のやりとりをするのはいうまでもない。能率化が求められる現代なのに、なぜ私たちはこんな手間をかけたことをするのだろうか?相手にダメージを与えるときでも同じことがみられる。書評で悪く書けば同じ仕打ちを受けるし、世界には「殺した者は殺せ」という復讐の慣行をもつ文明が近年まで存在したのも知られている。やればやり返される。このことは社会経済学では贈与交換ないし互酬性として知られている。市場での交換、国家(中央政府)による再配分とならんで社会経済の内には贈与交換の原理で動いている領域があるというのだ。けれども社会経済学で扱う互酬性は経済という狭い分野に限られている。相手も同じことをする条件で何かをするという行動は、私たちの生活でどこにでも見られる。たとえば一緒に生活するようになった男女のカップルにおいては、今晩の食事の後の皿洗いをどちらがするのか、というところにまで入り込んでいる。些細なようだが、このことはそう簡単には無視できない。贈与論の理論はマルセル・モースの「贈与論」に始まる。本書ももちろんモースの議論を取り上げるが、他のさまざまな議論も取り入れて拡張を試みる。限定交換と一般交換についてのレヴィ=ストロースの議論、あるいはベイトソンのダブルバインド論を導入すると、読者が想像もしなかったような形でカップルや家族の関係からグローバルな市場の変動まで、その政治性を含めた相互性の関係の広がりが見えてくることになる。相手も同じことをする条件で行動するときには循環的関係が出現するが、たいていは悪循環で私たちはその環に閉じ込められるし市場の変動(これも悪循環の一つ)に翻弄される。本書でアンスパックはどうしたら私たちが循環の輪の外に出られるか、そして悪循環を好循環に転換できるかを丹念に考察する。(訳者 杉山 光信)
内容説明
夕食後の皿洗いはどちらがするか、というカップル間の営み(互酬・贈与)からグローバルな市場での取引(等価交換)まで、「相手も同じことをするという条件」で何かを行うときには循環的関係が出現するが、たいていは悪循環で、私たちはその環の中に閉じ込められてしまう。著者アンスパックはM・モースの議論(贈与論)を発展させ、復讐をはじめ「相手も同じことをするという条件」でなされるさまざまな慣行や行為を取り上げて比較し、その相互関係をつきとめるという甚だ刺激的なやり方で議論を展開する。そして人にマイナスの影響を及ぼす循環的プロセスや因果関係をあらゆるところに見つけ出し、それが問題の根元であるとして、そこからいかにすれば抜け出し、悪循環を好循環に転換できるかを考察する。
目次
第1章 復讐と贈与(殺した者は殺せ;とても強力な取引;くれる人に贈る)
第2章 贈与とお返し(贈与の魔術;認識できないことを認識する;「第三の人物の謎」;循環する因果関係;ビールの奢り合いと背中側での手渡し;酒屋、肉屋、パン屋)
第3章 あなたと私(一人、神、あなた;チャタレイ夫人、その恋人、そしてジョン・トマス;グラスを洗うのは誰?;親、子どもたち、サンタクロース;第三の人物の場所;「賢者の贈り物」)
第4章 われわれと全体(両端を結ぶ;見えざる手による迷子;円環の復習)
著者等紹介
アンスパック,マルク・R.[アンスパック,マルクR.][Anspach,Mark Rogin]
1959年生まれ。ハーバード大学を優等(B.A.cum lauda)で卒業し、1988年にパリの社会科学高等研究院で博士(人類学)、1991年にはスタンフォード大学で学位(文学)を得る。現在はパリのエコール・ポリテクニク(理工科大学)に設置されているCREA(応用認識論研究センター)の研究員
杉山光信[スギヤマミツノブ]
1945年東京に生まれる。東京大学文学部卒業。東京大学新聞研究所教授を経て、明治大学文学部教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
cybermiso
takao
アルゴス
いとう・しんご