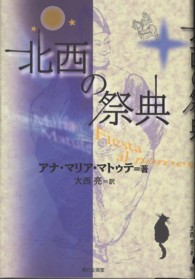出版社内容情報
企業のグローバル化と対峙してさまざまな攻防を繰り広げるローカルな市場のダイナミズム
グローバリゼーションは、同質化を推し進め、ローカルなものを押し潰し、多くの弊害をもたらすというのが大方の認識である。しかし、この認識にはグローバルなものが「強者」でローカルなものが「弱者」であるという暗黙の前提が潜む。ローカルなものは弱い存在であるから、グローバル企業がもたらす同質化の波に瞬く間に飲み込まれていく、というイメージをもつ人々も多い。筆者は、この10年余りの間、グローバル化の現場である「市場としてのアジア」を歩き多くのものを見てきた。ところが、そこで見た現実は、意外にもローカルな市場の「根強さ」であり「したたかさ」であった。アジア市場には、80年代から多くの日本の小売業が進出してきたが、市場の拡大とは裏腹に、その多くが撤退してしまっている。また、90年代の後半からは消費財メーカーがアジア市場に本格参入しているが、所得が増大し消費スタイルも西欧化しつつあるにも関わらず、商品が売れない、利益を出せないとするメーカーが多くみられる。さらに、グローバル化に成功したかのように見える企業でも、よく見るとローカルな市場の側に「同化」されていたり、まんまと取り込まれていたりするケースも見られるのである。つまり、ローカルな市場は企業が考えるほど甘くはなく、また反グローバリゼーション論者たちが考えるほど弱くもない。要するに、ローカルな市場は自律的な固有のダイナミズムを有しており、企業のグローバル化と対峙してさまざまな攻防を繰り広げているのである。このローカルな市場のダイナミズムを、本書では「市場の脈絡(コンテキスト)」と表現している。本書は、東南アジアの6つの市場をとりあげ、それぞれの市場に備わる脈絡(コンテキスト)を探り、それと企業との攻防を描くことで、アジア市場を読み解く糸口を提示しようとする試みである。本書により、アジア市場の「したたかさ」を味わって欲しい。
内容説明
アジアの人々はなぜ“買う”のか。企業のグローバル化と対峙して、様々な攻防を繰り広げるアジア市場の論理を読み解く。
目次
第1章 グローバル化とローカルな市場の脈絡
第2章 いま、東南アジア市場で何が起きているのか
第3章 タイの消費市場
第4章 マレーシアの消費市場
第5章 シンガポールの流通市場
第6章 インドネシアの消費市場
第7章 フィリピンの消費市場
第8章 ベトナムの消費市場
第9章 東南アジア市場がわかる七つの扉
著者等紹介
川端基夫[カワバタモトオ]
1956年、滋賀県生まれ。大阪市立大学大学院修了。経済学博士。龍谷大学経営学部教授。著書に、『小売業の海外進出と戦略』(新評論・日本商業学会賞)など(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。