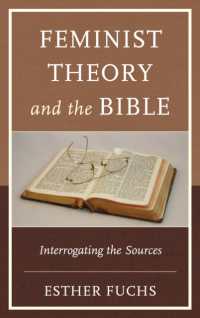内容説明
『社会のなかの子どもと保育者』の姉妹編。「地域に生きる子どもたち」をテーマに、前著よりもさらに具体的に子どもの姿を描き出し、社会学・文化人類学・教育学などの多分野にまたがる研究者それぞれの学問分野あるいは執筆者一人ひとりの得意とする研究手法を用いて執筆されている。
目次
子ども・家庭・地域の福祉と人間関係―「はじめてのおつかい」とソーシャル・キャピタル
地域で子育て支援―ファミリー・サポート・センター事業の可能性について
子ども会のゆくえ―地域社会の大人に課せられた課題
放課後、学童保育で育つ子どもたち
幼少期の子どもと地域スポーツ
世代間交流に寄せる地域の期待
三世代交流と子ども―子どもと老人の関係を問い直す
学校に求められる子どもの地域参加 生活科・総合的学習の可能性
地域の教育力とPTA活動
民俗文化にみる子ども観と成長―家族・地域・儀礼〔ほか〕
著者等紹介
小堀哲郎[コボリテツロウ]
秋草学園短期大学幼児教育学科教授。早稲田大学大学院人間科学研究科博士後期課程単位取得退学。博士(人間科学)。早稲田大学人間科学部助手、山村学園短期大学保育学科専任講師、秋草学園短期大学幼児教育学科准教授を経て、現職。専門は社会学(文化社会学、教育福祉論)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ゆう。
20
子どもは地域で生活し、学び、生きています。この本は、子どもの地域での人間関係の問題を社会学的に分析したものから、子育て支援、子ども会、学童保育、地域スポーツ、世代間交流、総合的学習の可能性やPTA、民族文化や祭りなど幅広く取り上げています。統一感はないですが、個々の論考には学ぶことが多い本でした。生活の私事化の広がりと消費社会化の広がりがあるなかで、子どもたちが地域でどのように成長・発達し、それを保障するのかという視点は、これからの子どもの権利を考えるうえで課題としてあるのだと思いました。2015/02/16