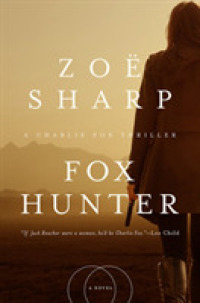内容説明
人道支援や開発援助は、誰の役に立っているのか?人助けと国益のはざまで揺れる「国際協力」の核心に迫る。
目次
第1章 国際協力のまなざし
第2章 国際協力の誕生
第3章 国際協力の表象
第4章 国際協力体験記を読む
第5章 国際協力の認識
第6章 援助批判・反批判を読む
第7章 国際協力の源流
第8章 開発の脱政治化を超えて
著者等紹介
北野収[キタノシュウ]
1962年東京都生まれ。獨協大学外国語学部交流文化学科教授。企業で世論調査・市場調査に従事。農林水産省で国際協力、農村整備、地域活性化、農業白書、行政改革会議等の業務を担当。日本大学助(准)教授を経て、2009年より現職。コーネル大学Ph.D.取得。専門は開発社会学、地域開発論、NGO研究。日本国際地域開発学会奨励賞、日本NPO学会優秀賞、日本協同組合学会学術賞受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
1.3manen
15
各章末にある、「確認しておくこと」だけ拾い読みしても 十分勉強になると思う。 時間の無い人は、そこから読んで、興味のある章にあたると よいだろう。 国際協力は目的であり、開発援助はその達成のための手段(15頁)。 エステバという人は、開発という単語に「低開発という不真面目な状況からの脱出」 というイデオロギーが付いて回るようになったのは1949年1月20日~という(20頁)。 細かいな。低開発を暗黙の前提とした開発なる概念が幅を利かせてきたという。 2014/03/27
うえ
6
「国際協力に従事してきたかつての農業技術者の多くは…近代化のための目標を達成するための技術を移植することを債務としてきた。一方、廣瀬の仕事は改良主義者のそれであったといえる。気候風土に培われてきたそれなりの科学的合理性を有する農民の在来技術に最大限の敬意を表しつつ、彼らの身の丈に近いレベルでの改良を行うという意味においてである。…持続可能性という形容詞がつこうと、生産性の向上、所得の増加、そして環境修復を遂行するという意味では、漸進的な近代化に技術をもって寄与するという構図は変わらない」2023/05/19
skunk_c
5
元農林官僚の研究者による「開発援助」論。まず多義性のある「国際協力」という言葉の使われ方の中から、70年代日本政府が「開発援助」の代替語として使い始めたことを確認。現場に関わった体験談や、様々な「開発援助」論、さらには援助に携わった先達の思想を意図的に「中立」な立場を意識して読み込み、このきわめて政治・政策的な事象が「脱政治化」することに注意を促す。著者はどうやら「内発的発展論」の立場のようで、「援助」される社会を視点の中心に置くべきと考えているようだ。哲学や歴史の領域を含め、批判的検討の必要を説く。2015/10/31
Akihiro Nishio
1
常識なのかもしれないが、ODAが戦後賠償の枠組みから生まれたこと、国際協力には戦前の植民政策の流れが含まれていることなど、知らなかったことが多くためになった。その中でも一番ためになったのは、国際開発分野での重要な文献を歴史的に考察するところ。これから最低限なにを読めば良いかわかった。2012/02/29
ぬめぬめ
0
「国際協力」という定着した言葉が持つ利他主義的なイメージとこの言葉が指す行為における国益主義等の実際上の政治性という矛盾を指摘し、批判的に捉え直すことの必要性を説く。「開発」「途上国への協力」という分野に興味を持つ一学生として感じる違和感や開発という行為・プロセス自体の意味などに答えているわけではないが、言語化する手助けにはなった。また、普段あまり触れない技術協力・農業分野の専門家の体験・開発観、日本の歴史的な文脈での「国際協力」の意味合いは非常に興味深く、日本人として生きる上で知るべきかなと感じた。2015/12/13
-

- 電子書籍
- ミルク進化論 なぜ人は、これほどミルク…