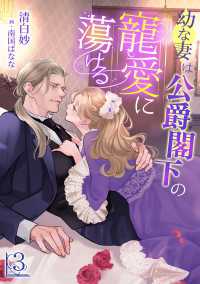出版社内容情報
触れられるだけで病気や対人ストレスが劇的に改善!介護や医療の現場で注目されるスキンシップケアの癒しの効果が明らかに。
内容説明
不調、ストレスの原因は「触れ合い」不足にあった!人に愛情を持って触れると、お互いの脳でオキシトシンというホルモンが分泌され、リラックスし、ストレスが癒され、絆が深まる。また、直接触れなくても、愛情を持って寄りそうだけで皮膚はお互いを感じ、癒しに向けた治癒力を発揮する。気鋭の身体心理学者が、知られざる皮膚の癒しの力に迫る一冊。
目次
第1章 コミュニケーションする皮膚(触れなくても肌は感じている;「直接触れ合う」と何が起こるか ほか)
第2章 触れないと皮膚は閉ざされる(失われた皮膚の交流;人の「なわばり」感覚 ほか)
第3章 病気やストレスが劇的に改善、スキンシップの驚くべき力(スキンシップが持つ癒しの力;境界が拓かれることで人は癒される ほか)
第4章 皮膚を拓いて、元気な自分を取り戻す(皮膚を拓いてつながりを拓く;笑うこと ほか)
著者等紹介
山口創[ヤマグチハジメ]
1967年、静岡県生まれ。早稲田大学大学院人間科学研究科博士課程修了。専攻は健康心理学・身体心理学。桜美林大学教授。臨床発達心理士。タッチングの効果やオキシトシンについて研究している。著書多数(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。