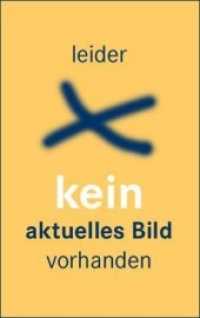内容説明
史上たった一人、二度にわたり将軍となった「足利義稙」、幕府に楯突き壮絶な最期を遂げた承久の乱の黒幕「法印尊長」、異郷をさすらい、刑死の憂き目を詩を唱えることで免れた傑僧「雪村友梅」―日本史上最も魅力的な時代である中世には、幾人もの知られざる才人、奇人が埋もれている。人名事典にさえ載っていない彼らの知られざる業績、型破りな生涯を膨大な史料から徹底的に掘り起こした、学殖ゆたかな名著。
目次
幕府に楯突いた院近臣 法印尊長(一一六六年‐一二二七年)
政治に深入りした歌人 京極為兼(一二五四年‐一三三二年)
中国で辛苦した傑僧 雪村友梅(一二九〇年‐一三四六年)
幕府がひれ伏した女院 広義門院(一二九二年‐一三五七年)
室町のマザー=テレサ 願阿弥(生年不詳‐一四八六年)
流れ公方 足利義稙(一四六六年‐一五二三年)
著者等紹介
今谷明[イマタニアキラ]
1942年京都生まれ。京都大学大学院文学研究科博士課程単位取得。文学博士。日本中世史専攻。横浜市立大学教授、国際日本文化研究センター教授を経て都留文科大学学長、現在、国際日本文化研究センター名誉教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
午睡
2
奇人とあるが、法印尊長、京極為兼、雪村友梅、広義門院、願阿弥、足利義材らはいずれも魅力的な人物である。限られた史料を駆使して、歴史の闇に埋もれた人々の軌跡と相貌をよく浮き上がらせていると思う。 たとえば足利義材。父である足利義視とともに美濃革手に下向し11年間同地に過ごし、時の運でたまたま将軍になるものの、クーデターに遭って座敷牢に幽閉されるなど、とくに引き込まれる。日野富子の引きで将軍になったものの、その日野富子に毒殺されかかるなど、義材の生涯の転変はいくらこの時代であっても驚くばかりの激しさだ。2019/12/02
でろり~ん
0
知らない人の興味深い話ばかりで面白い一冊でした。でも、著者はなんで奇人という表現をとったのでしょう。奇特な人ということではあるんでしょうけれど、誰もヘンな奴ではない印象でした。にしても、室町時代は、その始まりから終わりまで、入り組んで乱れて裂けて散るかも、ってな感じで理解しがたいほど複雑だなあと、再認識させられましたです。洞松院、初めて知りました。名前が、めしってすごいなあと思ってちと調べたら、一人娘の名前が小めし。ん~、もちろん大事なものなわけですが、女性の名前でめしって、ほほう、です。しかも戦国大名。2019/11/04
かずさん
0
マイナーな人物をわかりやすく書いていた。コンパクトで、とても読みやすかった。2020/04/19
パトリック
0
承久の乱の黒幕とされる法印尊長、歌人として有名ながら政治に深入りしすぎで配流先で客死した京極為兼、中国で永く囚人の憂き目を見た雪村友梅、結局室町幕府に北朝の再興のためい利用された光厳、光明帝の母の広義門院、戦争と飢饉による飢餓者に施しした願阿弥、浪々としつつ2度将軍位についた足利義稙、の活躍しながら意外と史書や小説で取り上げられない六人の生涯を信用できる史料を駆使して語ったもの。いわゆる「奇人伝」とは違うような気もするが…。2019/08/30