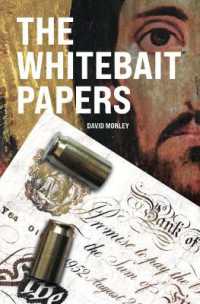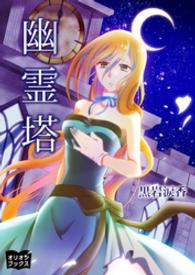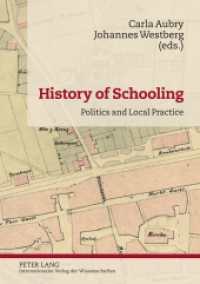内容説明
最後の将軍慶喜の孫娘に生まれ、高松宮妃殿下を姉にもつ著者が小石川第六天町の三千坪のお屋敷で過ごした夢のような少女時代を回想する。高松宮妃となる姉上が嫁ぐ日の記憶、夏休みの葉山や軽井沢へのお転地、四季折々の行事や日々の暮らしを当時の日記や写真とともに振り返る。戦前の華族階級の暮らしを伝える貴重な記録であり、四百年近く続いた将軍家に生まれた一人の女性の生き様を記した回顧録である。
目次
第1章 第六天育ち
第2章 おじじ様
第3章 姉妃殿下
第4章 思い出アルバム
第5章 お転地
第6章 女子学習院
第7章 嫁いでから
著者等紹介
榊原喜佐子[サカキバラキサコ]
1921(大正10)年、東京小石川第六天町の徳川慶喜家に一男四女の三女として生まれる。父は慶久、母は有栖川宮家から嫁した実枝子、姉は高松宮妃殿下喜久子様である。女子学習院を経て1940(昭和15)年、越後高田の榊原家当主政春氏と結婚。一男一女の母であり、四人の孫と曾孫がひとりいる(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
rokoroko
20
大河ドラマ「青天をつけ」見ていて昔慶喜公のお孫さんの書いた本読んだなと思い出した。出版された時話題となり読んだ記憶。残念ながら著者が生まれたときは慶喜公も実父もほどなくなくなってしまったらしい。ただ東京で夢のような生活をしていたのだなと思う。そのお金はどこから出ていたのか?「渋沢様にはお世話になって」と家令が話すシーンがある。50人もの人に囲まれ育つのはどんな風だったのか。私の母はそのころ貧乏人として生まれてたわけねと少しと皮肉な感想2021/06/20
夜の女王
20
「徳川おてんば姫」の流れでお姉さんの方の本を借りてきた。第六天町の屋敷で駆け回って遊んだという話は同じなのに、視点や書き方で性格の違いが垣間見えるのが面白い。喜佐子さんの方が日記をつけてたせいか、描写や観察が細かい。文章もよりたおやかで昔風の言葉遣い。日記の中でさえ、おたた様(母上)、お姉様、妹でさえ久美さまと敬語。育ちの違いを痛感する←当たり前(笑)!女性は人様の前で羽織り召してはいけないとか、お金を払う習慣がなかったので、お嫁に行ってからお店を出るときに支払いを忘れたとかの話にビックリだった。2018/09/17
Jiemon
4
念願叶って、小石川の旧徳川慶喜邸跡に行って来た。茗荷谷を望む三千坪の敷地は、その殆どが国際仏教大学院大学になっている。本に記載された邸宅の脇の坂道と玄関にあった大銀杏は現在も当時の面影を忍ばせる。当時はこの家に召使や請願巡査、書生を含めて50人程生活していたというが、1947年に三代目当主の徳川慶光が財産税の支払いができなくて国に物納された。筆者の妹が2018年に亡くなられて、この邸宅に住んでいた人の全てが亡くなったものと思われる。銀杏を見ながら時の移ろいを感じた。2020/08/22
Manami
3
「徳川おてんば姫」の久美子さんの1つ上のお姉さんの著書。第六天の夢のような暮らしから、結婚・戦争を経ての暮らしぶりなど。浮世離れした第六天から、戦後の暮らしと、ご苦労も多かった事だと思う。しかし、天真爛漫な子供時代のエピソードの数々、美しい言葉遣い、とても興味深かった。時代の流れの中で、お姫様ではいられなかった女性が、時代に真剣に向き合った、貴重な記録だと感じました。2020/10/26
あおい
3
図書館本。徳川家関係を読んだのでその流れで。。。ご幼少時にご両親をおたた様おとと様(夭逝)と公家風におよびあそばされていた日々のお日記とご回想。夢のようでいて活き活きとされていた雲上人のご生活、その後ご自身もご結婚され戦中~戦後と夢から冷めたような現実(空襲・食糧難など)のご生活がそれぞれ淡々と綴られています、ホンモノのお嬢様は、ご自慢話などされないのだな~と興味深く読了。双子のようにお育ちのお妹様とのツーショット写真がチコちゃんヘアなのがご一興。そのお妹様のご本もおありだとか、、、そのうち読みたい2019/02/09