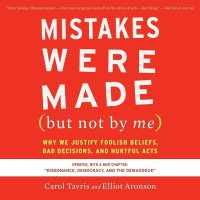内容説明
日本を「恥の文化」、欧米を「罪の文化」と規定して、日本人のアイデンティティに多大な影響を与えたベネディクトの『菊と刀』。だが、この本は敗戦国・日本を文化的に断罪すべく巧妙に練り上げられたプロパガンダの書だった。この本が書かれた背景、そしてベネディクト一流のレトリックを詳細に分析し、日本が恥の文化(=道徳的に欧米に劣った文化)の国と定義された真の理由を解き明かす。従来の日本文化論を根底から覆す労作。
目次
『菊と刀』の謎
ベネディクトの眼鏡―『菊と刀』は日本文化論なのか
「しかしまた」マインド・コントロール―戦時と平時の意図的な混同
ジキルとハイド―『菊と刀』以前のベネディクトの日本観
義理から恥へ―「恥の文化」の創作過程1
無我から無良心へ―「恥の文化」の創作過程2
罪の意識と戦争
真珠湾と「熊の親子」
「罪の意識のない日本人」誕生
「罪」対「恥」
ベネディクトはなぜ『菊と刀』を書いたのか?
ベネディクトの個人神話と米国神話
著者等紹介
長野晃子[ナガノアキコ]
東洋大学社会学部名誉教授。1938年生まれ。中央大学大学院文学科仏文学専攻博士課程満期退学。1976~77年フランス国立リヨン第三大学客員助教授、1987~88年フランス国立ストラスブール人文科学大学客員教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ekura
0
ベネディクトが骨子をジャーナリスト・バイアス『敵性日本』からとり、それを文化パーソナリティ論で和えて、アメリカの戦争加担への罪悪感を払拭するプロパガンダとして、また自身の就職のために『菊と刀』を書いたという論はわかりやすかった。それにしても、長野先生フランスでの12年間(1976~88)に、日本人ということでそうとうやなことあったのかな、と感じた。『日本辺境論』とも関連するだろうか。2010/03/22
ポルポ・ウィズ・バナナ
0
1870年からWW1にかけて、日本のみならず「ヨーロッパ各国」においても「伝統がつくられた」。つまり世界情勢の変化に伴い国体の再編成が急ピッチで行われたわけだ。日本の近年の軍事力の過信を、日本の国内政策ならびに国際政策における誤謬とし、得るところあまりに少なく、失うところあまりにも大。旧来の態度を捨て、国際協調と平和愛好とに根差した新たな態度を採用せねばならない。 2013/02/20
たぬき
0
目的のための 糞とミソの混ぜ方2009/11/26
-
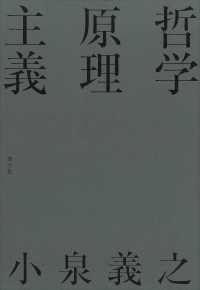
- 和書
- 哲学原理主義