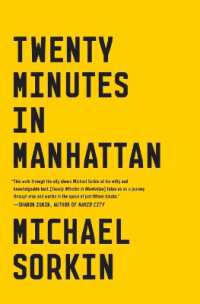内容説明
数ある野菜のなか、世界でトップクラスの生産高を誇るトマト。しかし、一般に食べられるようになったのは、わずか200年前のことだ。現代の食卓で最も身近な野菜、トマトには、興味つきない歴史が秘められている。起源はペルーかメキシコか。新大陸を発見したコロンブスはトマトを見たか。かのメディチ家にトマト料理のレシピはあるのか。そして、文明開化の日本にやってきた西洋野菜トマトは、どのようにして人々の食卓に取り入れられたのか―。各国を旅し、古い文献をひもときながら、世界でいちばん愛される野菜の謎に迫る。
目次
1 トマトを初めて食べた人々
2 トマトの故郷をたずねて
3 トマトは毒草か薬草か
4 トマトが野菜になった日
5 ケチャップのルーツは醤油と同じ?
6 醤油の国のトマト味
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
つみれ
14
トマトといえば、冷たいままでも温かくしてもおいしく食べられ、ソースにもジュースにもなり、あの赤い色は食卓を彩るだけでなく食欲増進の効果もあるということで、まさに万能野菜といった印象である。ところがこのトマトが世界で野菜として広く食べられるようになったのはつい200年ほど前のことで、それまでは毒草とみなされていたというのだから意外なことである。トマトが世界に伝播していく経緯が詳しく書かれていて興味深いが、それ以上に橘氏がさまざまな野生種トマト、栽培種トマトを求めて世界を旅するくだりがおもしろい。2015/02/15
nozma
1
かなりの取材と文献調査に基づいているのだろうと思わせる一冊。時代、国に関する記述が鮮やかで、飽きない。特筆すべきはほとんどの挿絵がカラーであるという点である。よくこの価格で出版できたものだと思う。2012/10/14
左近
1
本書はカゴメ株式会社創業100年を契機として企画されたものだそうな。著者が実際に各地を訪ね歩き、様々な資料にあたって、トマトの原産地から、いかに食用となり、世界に広まっていったかを追っている。小難しい学術書ではなく、知的好奇心を刺激される楽しい読み物。歴史上の様々なレシピも載っているので、料理好きな方は、自分で作ってみたくなるのでは。2012/02/14
桃水
1
トマトが野菜として食べられるようになっただけでなく調味料(サルサ、トマトソース、ケチャップなど)として広まっていったことに関連して醤油の歴史にも触れているのが嬉しい。2009/12/27
kinaba
0
不正確な情報源にならないようしっかり気を使って書かれているのが随所から感じられる。地味だけど地道なトマト史書。2013/02/26
-

- 電子書籍
- 絶代武神~伝説の始まり~【タテヨミ】第…