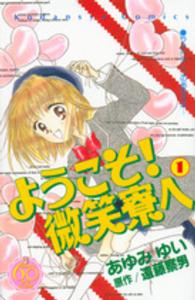内容説明
なぜオウム真理教事件はこれほど人々の関心を引きつけたのか―。著者は、戦後25年目に起こった全共闘運動を自らの体験を踏まえて内省しつつ、戦後50年目に起こったオウム事件の必然性を鮮やかに読みといてゆく。また、左翼崩壊以降の知識人がオウムのような新々宗教にたいしてどのような態度をとってきたか、いま「信じる」とはどういう意味をもつのかという問題にも光を当て、現代日本社会が抱える深い空洞をあぶりだしてゆく、エキサイティングな書。
目次
1章 オウムという断層
2章 全共闘運動とは何だったのか
3章 全共闘批判からオウムへ
4章 オウムと知識人―吉本隆明ほか
5章 オウムと知識人―宗教学者たち
6章 いま「信じる」とは何か
7章 文化と思想のハルマゲドン
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
ふみあき
60
全共闘はおろかオウム真理教も、もはや「歴史」の範疇に入ってしまったが、本書はオウム事件が現在進行形の渦中で書かれた論考集。本書の白眉はなんと言っても、かつての師匠である吉本隆明を始め、オウム派(?)知識人たちへの苛烈な批判だ。吉本は麻原彰晃を「世界有数の宗教家」と持ち上げていたが、突出してヒドいのが山崎哲で、「我われが見失っている生命を露出させるためだったら、サリンを撒くっていう方法も『あり』なんだ」という問いかけを是とした。浅田彰への罵倒芸も堂に入ったもので、この時期の著者は評論家として一番切れていた。2025/07/02
テツ
16
学生運動もオウムもアホが集まり狂気が凝縮されて至ったテロ組織でしかないのに、そうした奴らに対してある程度好意的な評価を下していた文化人の方々が存在していたことに驚愕するよな。いつの時代でも反体制的なイデオロギーさえ見出せればそれを正義だとする困った人間っているんだな。どちらもそれなりに時間が経過してしまった出来事だけれど、当時の時代の空気がそれをどう扱っていたのかを知ることは大切だと思います。こうした在り方をした集団は力をつける前にきちんと社会がNOを突きつけて力を削がなければ歴史は繰り返す。2021/10/21
TURU
3
難しい文章の羅列で何が言いたいのか全く伝わってこない。自分の読解力の無さもあるのでしょうが、同じオウムを扱った本を出している一橋文哉などは先を読みたたせるセンスがある。とても良い題材なのにセンスのない人間が書くと面白さの欠片もない。もっと勉強してから読め!と言われそうだが。2014/07/27
大熊真春(OKUMA Masaharu)
2
難解な部類の評論本。◆「オウム」を「全共闘」と比較して考察するものと思って読んだが、まず初めの1/3は全共闘の話だけ。いつで出てくるかと待ちわびてやっと「オウム」になったら今度はオウムのことだけ。結局私には「オウム」と「全共闘」には何の関連もない、と思えてしまった。◆緻密で正確な論理展開をしているんだと思うが、今のアタマの鈍くなった私にはちょっとつらい頭のさえてた中高生のころだったら楽しい本なんだろうけど。◆頭がいい人でないとムリ。◆ふた昔前の大学入試現代文くらいの難しい文が200ページ続くと思えばいい。2014/06/24
Atsushi Iwata
2
地下鉄サリン事件発生直後から雑誌に寄稿された著者のオウム関連の文章を集め、加筆して1995年末に出版された本ということで、当時この事件がメディアや知識人にどう受け止められ論じられていたかが時代の空気ごとパッケージされてる。「へぇあの人がこんな教団寄りの発言を」という驚きも随所にあったけれど、むしろ全体としてはいまだ狂騒の中にある時期に書かれたとは思えないくらいに俯瞰的。特に全共闘との対比をはじめ信者の心性を分析した内容には現在における全く別の事象にもそのまま援用できそうな部分も多く、興味深かった。2014/03/01