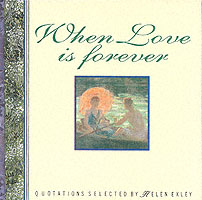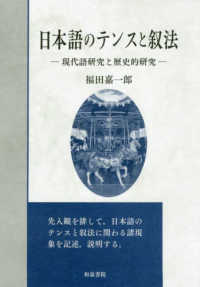内容説明
真珠湾奇襲の報せを受けたチャーチルは、「これで勝った」と安堵した。蒋介石もまた同様だった。アジアの紛争にアメリカを引き込んだ時点で、日本との戦いの結末はすでに見えたのである。問題は早くも「戦後」の体制へと向かいはじめる。誰が戦後世界において覇権をかち得るのか。そして植民地帝国の将来はどうなるのか―連合軍として眼前の対日戦に臨む米英そして中国は、一応は同盟関係にありながらも、水面下では戦後世界を見据えたもうひとつの闘いを繰り広げていたのである。広範な資料を編み上げてこの巨大な戦争の全体像を描き出すと同時に、書簡や日記などに現れた肉声を通じて、ローズヴェルトやチャーチル、蒋介石ら各国首脳の生々しい人間像にも迫る。米バンクロフト賞を受賞した太平洋戦争研究の最重要書である。
目次
第1部 真珠湾前
第2部 真珠湾からカサブランカへ 一九四一年十二月―一九四三年一月
第3部 カサブランカからカイロへ 一九四三年一月―一九四三年十二月
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
skunk_c
52
アジア太平洋戦争に関する、アメリカとイギリスの政治家、外交官、軍人達の発言や私信などを詳細に分析した書。チャーチル、ローズヴェルトといった指導者だけでなく、官僚などの考えも考察の対象とされ、植民地帝国イギリスと、新興勢力のアメリカの思惑の違いがよく分かる。しかもそれぞれの国に様々な考えが入り乱れていた様子も。さらにオーストラリアやインドといった帝国を構成する国や地域の動向、あるいは植民地に関する考えの違いなど、現代史を考えるためのひとつの基礎も見ることができる。ただしあまりに詳細なので読むのは大変だが。2020/11/22
フンフン
1
太平洋戦争中の連合国内での確執を描く。スチルウェル日記やチャーチルやウェデマイヤーの回顧録でわかっていたことが多い。インド人が英軍に非協力的だったのは当然として、オーストラリアも自国が日本の侵略の脅威にさらされているときに、地中海や中東方面に出兵させられることに非常な不満を抱いて、国防を英国よりも米国頼みのほうに傾いたことを知ったぐらいが本書からの収穫。2019/03/19