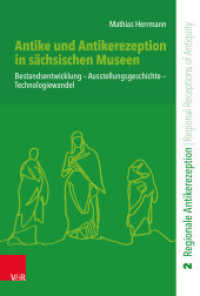出版社内容情報
未解明だった一万石を少し超える程度の譜代小藩の支配の実態を解明する画期的な業績。藩政史料がない中での研究への道を切り拓く。和泉国に陣屋を置いた譜代小藩・伯太藩とその藩領社会の実態を把握するため、藩家臣団と陣屋の構造、陣屋元村と藩領社会との関係、藩領社会の村落構造の展開を具体的に関連させつつ分析する。これまでまったく未解明だった一万石を少し超える程度の譜代小藩の支配の実態を解明する画期的な業績であり、藩政史料がない中での今後の譜代小藩研究への道を切り拓く。
序 章
一 近世畿内の陣屋元村について
二 藩領社会の構造と村社会の把握
三 対象地域の概要と本書の構成
第?部 伯太藩の陣屋と藩領村々
第一章 伯太藩の家中形成と大坂定番 ――「家老」家々の来歴から――
はじめに
一 伯太藩と渡辺家「家中」の構成
二 由緒書からみる「家老」家々の来歴
三 一七世紀大坂での「家中」召し抱え
おわりに
第二章 伯太藩による藩領支配の展開
はじめに
一 享保期までの伯太藩
二 畿内移転後の陣屋変遷と領内支配
三 伯太藩財政と触頭・郷惣代
おわりに
第三章 伯太陣屋と陣屋元村
はじめに
一 近世伯太村の空間構成
二 陣屋移転と伯太村
三 陣屋元村の都市性と村落秩序
おわりに
第四章 大坂定番期の武家奉公人調達 ――泉州上神谷郷を対象に――
はじめに
一 定番期の屋敷奉公人確保
二 上神谷郷における屋敷奉公人の出願状況
三 豊田村における屋敷奉公人減少とその背景
おわりに
第五章 伯太陣屋の武家奉公人調達と所領村々
はじめに
一 伯太藩の奉公人徴発と郷の対応――陣屋元下泉郷を中心に
二 村々における出人確保
三 与内支給をめぐる奉公人・郷・藩の利害
おわりに
第?部 伯太藩領の村落構造――泉州泉郡を中心に
第六章 泉州泉郡平野部における相給村落の成立 ――池上村を事例として――
はじめに
一 池上村における文禄三年検地
二 集落と捌き高
三 大村・かいと村統合期の庄屋
四 一八世紀前半の「本郷」と「出作」
おわりに
第七章 山里春木川村の村落秩序と山用益
はじめに
一 近世春木川村の山と耕地
二 村山における用益の展開――文政期の山論から
三 近世末?明治期初頭の山の用益――蜜柑畑開墾をめぐって
おわりに
補論 一九世紀伯太藩領の倹約令と「村方取締書」
はじめに
一 一九世紀春木川村の「村方取締書」
二 上神谷郷「郷中申合倹約之事」と豊田村の村方取締書
三 村方取締書の作成過程と領主規制
おわりに
終 章
一 伯太藩の展開と「陣屋元地域」の形成
二 村落社会の変容と藩領社会――陣屋元の下泉郷を中心に
齊藤 紘子[サイトウ ヒロコ]
著・文・その他
目次
第1部 伯太藩の陣屋と藩領村々(伯太藩の家中形成と大坂定番―「家老」家々の来歴から;伯太藩による藩領支配の展開;伯太陣屋と陣屋元村;大坂定番期の武家奉公人調達―泉州上神谷郷を対象に;伯太陣屋の武家奉公人調達と所領村々)
第2部 伯太藩領の村落構造―泉州泉郡を中心に(泉州泉郡平野部における相給村落の成立―池上村を事例として;山里春木川村の村落秩序と山用益;補論 一九世紀伯太藩領の倹約令と「村方取締役」)
著者等紹介
齊藤紘子[サイトウヒロコ]
1983年京都府生まれ。2011年大阪市立大学大学院文学研究科日本史学専修後期博士課程修了。日本学術振興会特別研究員(PD)。大阪市立大学都市研究プラザ特別研究員を経て、京都精華大学人文学部総合人文学科講師。博士(文学)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 洋書
- TALISMAN
-

- 電子書籍
- ヤンキーに恋と育児はムズすぎる【マイク…