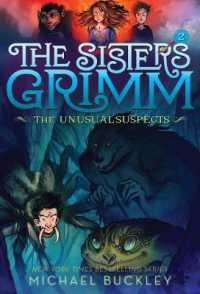出版社内容情報
泣ける映画」はどこから来て、どこへ行くのか
メロドラマの想像力は過ぎ去った流行ではなく、現在の表象のなかにも確実に息づいている。その射程はどこまで届くのか。稀代の書き手が遺した、可能性に満ちあふれたテクストたち。解説・木下千花
内容説明
メロドラマの想像力は過ぎ去った流行ではなく、現在の表象のなかにも確実に息づいている。その射程はどこまで届くのか。稀代の書き手が遺した、可能性に満ちあふれたテクストたち。
目次
1 メロドラマの力―概念と受容(「メロドラマ」映画前史―日本におけるメロドラマ概念の伝来、受容、固有化;メロドラマ映画研究の現在 訳者解説 ジョン・マーサー、マーティン・シングラー『メロドラマ映画を学ぶ―ジャンル・スタイル・感性』)
2 メロドラマに輝くもの―日本映画、あるいは幾人かの女優(「わたし、ずるいんです」―女優原節子の幻想と肉体;変化する顔、蝶の身体―京マチ子のスター・イメージに見る倒錯的従順さ;『君の名は』とは何か―ブームの実態とアクチュアルな観客;語らざる断片の痺れ―メロドラマとして見た清順映画 ほか)
3 メロドラマは拡散する―作家性とエスニシティ(映画における「仕方がないこと」のすべて?―『ヴァンダの部屋』について;思春期、反メロドラマ、自己言及性―ソフィア・コッポラの作家性にかんする二、三の事;ハイパー・メロドラマ―映画『バーフバリ』の凄まじさに見る雑種性、抽象性、超政治性;「初恋」の行方―現代韓国恋愛映画論 ほか)
著者等紹介
河野真理江[コウノマリエ]
1986年東京生まれ。映画研究。立教大学大学院現代心理学研究科映像身体学専攻博士課程修了。博士号(映像身体学)取得。立教大学兼任講師、青山学院大学、早稲田大学、東京都立大学、静岡文化芸術大学非常勤講師を歴任。著書に『日本の“メロドラマ”映画―撮影所時代のジャンルと作品』(森話社、2021年、第13回表象文化論学会賞奨励賞を受賞)がある。2021年死去(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Ahmad Hideaki Todoroki
はしご
よっちん