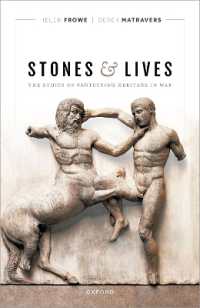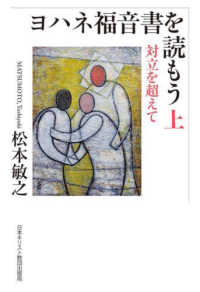出版社内容情報
キツネは犬になれるか?
シベリアの奥深くに、尾を振り、耳が垂れている、友好的で従順な動物がいる。しかし、外見に反して彼らは犬ではなく、キツネである。これは、何千年もの進化をわずか数十年で再現した史上最も驚くべき繁殖実験の成果だった。本書は科学者たちの驚くべき物語を描くのと同時に、時間を超えて人間と動物を結びつけてきた深い絆を讃える。
内容説明
極寒の地シベリアで行われたキツネの家畜化実験。登場人物は科学者と愛らしいキツネとその世話係。そして実験の詳細、政治的陰謀、避けられた悲劇と避けられなかった悲劇…。その全貌がいま明らかになる。
目次
序論 なぜキツネはイヌのようになれないのか?
1 大胆なアイディア
2 もう火を吐くドラゴンはいない
3 アンバーの尾
4 夢
5 幸せな家族
6 繊細な相互作用
7 言葉とその意味
8 SOS
9 キツネのように賢く
10 遺伝子の激変
著者等紹介
ダガトキン,リー・アラン[ダガトキン,リーアラン] [Dugatkin,Lee Alan]
ルイビル大学の生物学科教授、科学史家
トルート,リュドミラ[トルート,リュドミラ] [Trut,Ludmila]
シベリアのノボシビルスクの細胞遺伝学研究所の進化遺伝学教授。1959年以降キツネの家畜化実験の主任研究者
高里ひろ[タカサトヒロ]
翻訳家。上智大学卒業(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
tom
21
キツネは凶暴な獣だ。でも、ときどき大人しいキツネが現れる。60年前、動物学者ベリャーエフは、大人しいキツネを純粋培養したらどうなるかと考えた。そして、やってみた。わずか30年後、キツネは家畜になり、人と戯れ、人に群れようとする。顔つきは犬に似てくる。丸っこくて可愛らしい。オキシトシンが溢れ出る。ここまで読んで、人も家畜化されたサル科動物なのかと思ったら、その後の頁は、これの証明。人が群れる、周囲を気にする、賢くなる、すべて家畜化の現れだったのだ。これが人のおおもとの根っこ。なるほど思う。今年最初の面白本。2025/01/31
フク
12
#読了 2023年発行 1950年代から現代まで至るキツネの家畜化を試みる物語。人に懐く姿は文字だけでも可愛い。 〈われわれは家畜化された、正確に言えば自己家畜化された霊長類なのだ〉 図書館。2024/03/02
読書一郎
10
オオカミがイヌに進化したように、キツネを飼いならして「イヌ化」することができないか…今から80年前に、そんな突拍子もないことを思いついた生物学者がいました。おとなしいキツネ同士をかけあわせ、それを何世代か続けてゆく。やがてキツネはイヌのように「進化」するのではないか…なんと実験は大成功し、人になつき、従順なキツネが続々と誕生します。本書は、この驚くべき実験の経過を描いたノンフィクションです。実験は今も継続中で、開始当初にはなかった技術―遺伝子の解析なども行われているらしい。すごい内容の本でした。2024/01/21
nobu23
4
何世代にも渡って人間に友好的な狐を交配させて家畜化するのかといった、テーマに取り組んだロシア人学者の話。 生まれつき人間に友好な狐が誕生し、身体的特徴も変化するという驚きの結果や様々な考察がされていて面白い。2024/01/02
於千代
3
キツネの家畜化実験の試行錯誤。従順性を人為選択することで驚くほど短期間でキツネが人に慣れていく過程をみることができた。 キツネと実験者の交流や、家畜化の推論も興味深かったが、それよりも研究環境の悪さに目が行ってしまった。 ルイセンコ全盛期の研究への弾圧や、ソビエト崩壊による資金難など、決して恵まれている環境ではないにも関わらず、40年に渡って実験を継続し続ける熱意に頭が下がる思いがした。2024/12/31