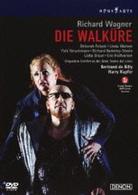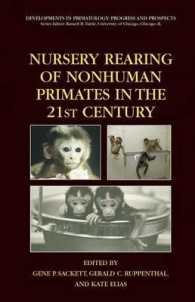出版社内容情報
一つの種が絶滅するとはどういうことか。ダナ・ハラウェイ氏、マーク・ベコフ氏推薦。
絶滅とはある特定の種の最後の一個体が死ぬことを意味するのではない。絶滅はそのはるか前からなだらかに、しかし着実にはじまっているのだ。絶滅の過程にいる種と人間はいかなる関係が結べるのか。消えゆく種に配慮するとはどういうことか。絶滅の過程で人間が負いうる義務とは何か。すでに多くのことが語られてきた絶滅をめぐる問題を、絶滅にむかう五種の鳥たちの生から問い直す。解説・近藤祉秋
内容説明
絶滅とはある特定の種の最後の一個体が死ぬことを意味するのではない。絶滅はそのはるか前からなだらかに、しかし着実にはじまっているのだ。絶滅の過程にいる種と人間はいかなる関係を結べるのか。消えゆく種に配慮するとはどういうことか。絶滅の過程で人間が負いうる義務とは何か。すでに多くのことが語られてきた絶滅をめぐる問題を、絶滅へむかう五種の鳥たちの生から問い直す。
目次
はじめに 「絶滅の縁」でいきいきと物語を語ること
第1章 アホウドリの巣立ち―空の飛び方と無駄にされた世代
第2章 旋回するハゲワシ―「絶滅のなだらかな縁」における生と死
第3章 都会のペンギンたち―失われた場所の物語
第4章 ツルを育てる―飼育下生活の暴力的‐ケア
第5章 死を悼むカラス―共有された世界における悲嘆
エピローグ 物語の必要性
著者等紹介
ヴァン・ドゥーレン,トム[ヴァンドゥーレン,トム] [van Dooren,Thom]
1980年生まれ。シドニー大学人文学部准教授。環境哲学者。とりわけ、種の絶滅や絶滅の危機に瀕している種と人間の絡まり合いの中で生じる哲学的、倫理的、文化的、政治的問題に焦点を当てて研究をしている。エリザベス・デローリー、デボラ・バード・ローズと共に学術誌Environmental Humanities(Duke University Press)の創刊と編集に携わっている
西尾義人[ニシオヨシヒト]
1973年東京生まれ。翻訳者。国際基督教大学教養学部語学科卒業(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
takao
ハル
志村真幸