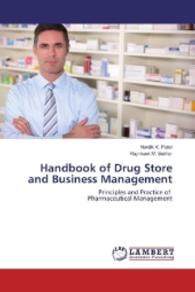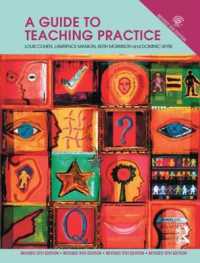出版社内容情報
「治る」と「治らない」のはざまで。
1990年代以降、都市部を中心に雨後の筍のごとく急増したメンタルクリニック。心身の不調から日常的な悩みまで「メンタル」をめぐるさまざまな問題が持ち込まれ、必要に応じて診断や治療がなされる。
メンタルクリニックへの接近と離反を繰り返す患者、そしてそれに寄り添うスタッフへのインタビューを主軸に、現代の自己変容のかたちを紐解く。生きづらさをかかえる人びとに寄り添う社会学。
内容説明
1990年代以降、都市部を中心に雨後の筍のごとく急増したメンタルクリニック。心身の不調から日常的な悩みまで「メンタル」をめぐるさまざまな問題が持ち込まれ、必要に応じて診断や治療がなされる。メンタルクリニックへの接近と離反を繰り返す患者、そしてそれに寄り添うスタッフへのインタビューを主軸に、現代の自己変容のかたちを紐解く。生きづらさをかかえる人びとに寄り添う社会学。
目次
序章 メンタルクリニックの社会学
第1章 メンタルクリニックの誕生
第2章 不安定な医療化―何を医療とみなすのか
第3章 トラブルの「実在」をめぐる問い
第4章 治療する自己―薬・脳・こころをめぐる語り
第5章 「治る」と「治らない」のはざま
終章 メンタルクリニックの「出口」
著者等紹介
櫛原克哉[クシハラカツヤ]
東京大学大学院人文社会系研究科社会文化研究専攻博士課程修了。博士(社会学)。専門社会調査士。日本学術振興会特別研究員(DC2)を経て、現在、東京通信大学情報マネジメント学部講師(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Asakura Arata
sk
rune
Jau
渡辺 にゃん太郎