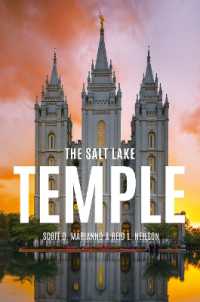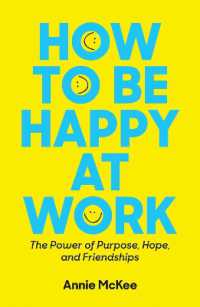出版社内容情報
中立的なものこそ政治的である。
なぜ文書は改ざんされたのか。なぜ官僚は忖度するのか。官僚制をめぐる問題とその背景を、たんなる時事問題としてではなく、日本の空気や感情論としてでもなく、政治学の問いとして考える。ウェーバー、シュミット、アーレント、キルヒハイマー、ハーバーマス、グレーバーを深く「読み」、いま「使う」ために。
野口雅弘[ノグチマサヒロ]
著・文・その他
内容説明
中立的なものこそ政治的である。現代を読み解くための政治思想。なぜ文書は改ざんされたのか。なぜ官僚は忖度するのか。官僚制をめぐる問題とその背景を、たんなる時事問題としてではなく、日本の空気や感情論としてでもなく、政治学の問いとして考える。ウェーバー、シュミット、アーレント、キルヒハイマー、ハーバーマス、グレーバーを深く「読み」、いま「使う」ために。
目次
今日の文脈
1 文書主義(官僚制と文書―バルザック・ウェーバー・グレーバー)
2 「決められない政治」とカリスマ(脱官僚と決定の負荷―政治的ロマン主義をめぐる考察;「決められない政治」についての考察―カール・シュミット『政治的ロマン主義』への注釈;カリスマと官僚制―マックス・ウェーバーの政治理論へのイントロダクション)
3 合理性とアイヒマン(合理性と悪;フォン・トロッタの映画『ハンナ・アーレント』―ドイツの文脈;五〇年後の『エルサレムのアイヒマン』―ベッティーナ・シュタングネトとアイヒマン研究の現在)
4 動員と「なんちゃらファースト」(テクノクラシーと参加の変容;「なんちゃらファースト」と悪)
5 キャッチ・オール・パーティと忖度(官僚主導のテクノクラシー―キルヒハイマーの「キャッチ・オール・パーティ」再論;忖度の政治学―アカウンタビリティの陥穽)
中立的なものこそ政治的である
著者等紹介
野口雅弘[ノグチマサヒロ]
1969年生まれ。早稲田大学大学院政治学研究科博士課程単位取得退学。哲学博士(ボン大学)。成蹊大学教授。専門は、政治学・政治思想史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
とある本棚
Monsieur M.
Bevel
saiikitogohu
chiro