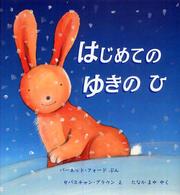内容説明
人間の精神は思想・学問・制度・権力にとりまかれてきた。そこから社会制度や医療現場が形づくられるとして、そこで人間と「狂気」とはどのように取り扱われているのだろうか。歴史を透徹したまなざしでとらえかえし、人間の精神と社会との関係を、未来にまで射程をひろげながら思考する。
目次
1(精神衛生の体制の精神史―一九六九年をめぐって)
2(過渡期の精神;狂気の哲学史へ向けて―行動の狂気と自閉症・発達障害・精神病圏;精神と心理の統治)
3(人格障害のスペクトラム化;自閉症のリトルネロへ向けて)
4(自殺と狂気―リベラリズムとモラリズムにおける;狂気を経験する勇気―木村敏の離人症論に寄せて)
5(精神病理をめぐる現代思想運動史)
あとがきに代えて―狂気の真理への勇気
著者等紹介
小泉義之[コイズミヨシユキ]
1954年札幌市生まれ。東京大学大学院人文科学研究科博士課程哲学専攻退学。現在、立命館大学教授。専攻は、哲学・倫理学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
-

- 電子書籍
- 週刊ベースボール 2018年 4/9号
-

- 電子書籍
- 勇者の元カノです【タテヨミ】第65話 …