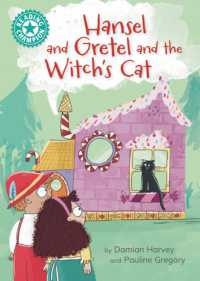出版社内容情報
藤野寛[フジノヒロシ]
内容説明
近年注目の哲学者ホネットの「承認」論から出発し、ルソー、カント、アドルノなどの哲学界の巨人の議論、さらには村上春樹の小説や現代のSNSなどの事例にいたるまで、多彩な角度から社会的存としての人間の根本に迫る。
目次
第1章 導入―他者に認められること/他者を認めること(ありのままの自分を生きること/人目を気にして生きること;「認める」という行為、あるいは村上春樹の出現について ほか)
第2章 基礎的考察―「社会性」をめぐる考察へ(承認が認識に優先する;「社会性」とはどういう性質か)
第3章 体系―承認の三つの型、そして寛容(愛―承認の三つの型(1)
人権の尊重(差別との闘い)―承認の三つの型(2) ほか)
第4章 思想史的対話―尊重・寛容・承認(ルソー;カントとエルンスト・トゥーゲントハット ほか)
第5章 展開―承認論はどこに向かうか(「承認」の胡散臭さ(両義性)
コミュニケーション(社会的生)とは闘争である ほか)
著者等紹介
藤野寛[フジノヒロシ]
1956年生まれ。京都大学大学院文学研究科博士課程学修退学。フランクフルト大学学位取得。現在、國學院大學文学部教授。専門は哲学・倫理学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ゆう。
40
ホネット「承認論」の解説本に近いかもしれません。人は他者との関係性にあり、認められたいという欲求を満たされることによって自己を肯定することにつながります。承認論の積極的に学ぶ点はそういう点だと思います。ただ承認は闘争を通じて得られるというところは、その闘争の意味を深く考えなければならないと思いました。そしてその闘争が社会進歩とどういう関係があるのかということも。承認論は魅力的ではありますが、観念論的な面が強いようにも感じます。難しいですね。もっと学ばなければ。2018/11/03
踊る猫
33
実に刺激的な問題設定で中身を成す議論もわかりやすい。物静かなトーンに著者の誠実さがうかがえる。だが、書かれていることがらを追おうとしてもどこか隔靴掻痒に感じる。ひとえにこれはぼく自身がこの本で中心的に引かれているホネットやアドルノを知らないからというのもあるのだろう。だが、著者の議論がまだまだここから伸びを見せるのではないかという「予感」にとどまっている印象は否めない。心理学的につなげていくのか、社会学や政治哲学に接続していくのか。その意味ではなかなか「惜しい」1冊のようにも。いつか再チャレンジするかな?2024/12/22
テツ
24
ぼくはあまり他人に興味がないけれど承認欲求に縛られ苦しんでいる方々はその呪縛から逃れるために読むとよいかもしれない。人は大なり小なり違いはあれども他者との関係性の中からしか自分を見出すことはできない。それは確かにそうなのだけれど不特定多数からの承認を得なければ満足できずに不安だというのならそれはもはや精神疾患と呼ぶのだろう。認められたいのなら認めること。リアルな自分とリアルな相手との間に相互に緩やかに承認し合う空気を創ること。きっとそれは恋人でも友人でも家族でも変わらない大切なこと。忘れずにいたいですね。2020/06/16
pino
6
「人の役に立ちたい」という気持ちに、「自分が認められるために」という思いが混ざっていないか常に自問している。カントの定言命法「他者の存在を私にとっての手段・道具と見なさない」への倫理的な葛藤なのだろう。一方で本著は、承認欲求を社会的存在である人間が本性的に持つものとはっきり肯定している。承認欲求の根っこは何か。それは自尊感情であろう。自分が行為して善しと思うもの、美しいと感じ、普遍性にも通ずること。それを支えるのが他者の承認なのではないだろうか。いやいや、まだまだ未消化で、奥が深いぞ、承認論。2019/06/17
sk
5
ホネットの議論をベースに、愛・人権尊重・業績評価など社会に対する基本的態度である承認について論じている。良書。2018/12/09